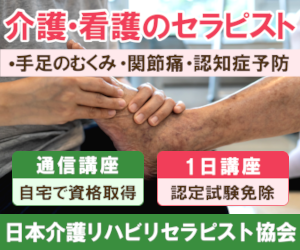サンデーホリデーの日
半ドンの日とも呼ばれます。
1876年の今日、官公庁で土曜を半休、日曜を休日とする太政官布告が出されました。
それまでは31日を除く1と6のつく日をお休みにしていたそうです。
土曜日を半ドンという由来は、
①1871年(明治4)から皇居で正午に大砲を撃つようになり、土曜は大砲のドンと共に仕事が終わるので、丸の内勤務の人の間で「半ドン」と呼ばれるようになったのが全国に広がった。
②オランダ語の日曜日をzontag(ゾンターク)といいますが、それがドンタクに訛り、土曜日の半分休み→半ドンタク→半ドンとなった。
など、諸説あります。
スイーツの日
3(Three=ス)1(イ)ー2(ツ)の語呂合わせ。
全国の銘菓や郷土のおやつ、ご当地スイーツなどにまつわるクイズです。
お住まいの地域を離れると難しい問題もあるかも。
【北海道】ラングドシャクッキーにホワイトチョコをはさんだお菓子は「白い~」
【答】白い恋人
【青森県】ある海の生き物の名前がついていますが、材料は製粉した津軽米、砂糖、餡を混ぜて蒸したものです。くるみがはいっています。
「~餅」といいます。
【答】久慈良(くじら)餅
【秋田県】藩主佐竹氏に献上したとき「もろもろの菓子を超えて美味」と言われたことがこのお菓子の名前の由来。夏に食べる黄色くて甘い野菜とは別のものです。
【答】もろこし(諸越)
【岩手】小麦粉と塩と水を練ったせんべいで鋳型で焼きます。ゴマや落花生などいろいろな種類があります。
「~せんべい」といいます。
【答】南部せんべい
【山形】本来柚子を入れるのですが、入手が難しかったことで代わりにくるみを入れて作った餅菓子。「くるみ~」といいます。
【答】くるみゆべし
ゆべしは漢字で書くと「柚餅子」。柚子が入っていますね。
【宮城】枝豆で作った緑色の餡が美しい餅菓子。伊達政宗が名付けたとも言われています。「~餅」といいます。
【答】ずんだ餅
【福島】奥州街道郡山の茶屋発祥のお饅頭で、日本三大饅頭のひとつです。
黒糖の入った皮で餡を包んでいます。「柏屋~饅頭」といいます。
【答】柏屋薄皮饅頭
【茨城】サツマイモを蒸して切って干して作ります。そのまま食べてもおいしいですが、ケーキの生地に混ぜて焼いたりアレンジもできます。
【答】干し芋
【栃木】まるでかりんとうをかじっているような揚げたてにカリカリの皮が特徴のお饅頭です。かりんとう饅頭を略したような名前。
【答】かりまん
【群馬】サクサクのおせんべいでミルククリームをはさんだ歯あたりのよいお菓子です。名前は神話の八咫がらすに由来しています。
【答】旅がらす
【千葉】千葉県の名産品である落花生を使った最中です。
【答】ぴーなっつ最中
【埼玉】もち米を蒸して乾燥したものに、水あめや砂糖を加えて棒状に伸ばし、きな粉をまぶしたものです。江戸時代からある銘菓です。
名前の由来ははっきりしていません。元々は「~棒」だったのではないでしょうか?
【答】五家宝(ごかぼう)
【東京】カステラ生地で餡を包んだお菓子で、七福神や五重塔などいろいろな姿をしているのが特徴。浅草を中心に売られていますが、元々は別の町が発祥で名前もその町の名前からきています。「~焼き」
【答】人形焼き
【神奈川】鎌倉の鶴岡八幡宮の「八」の字から発想を得たデザインのお菓子。
明治時代から現在まで神奈川銘菓といえばこれ。

【答】鳩サブレ
【山梨】うぐいす餡を黒糖羊羹で包んでまん丸く玉の形にした美しいお菓子。
昭和4年に誕生したロングセラーお菓子です。
名前は見たまま。
【答】くろ玉
【長野】干し柿生産量日本一は長野県です。
産地の名前が付けられたこの干し柿は過去には皇室にも献上されています。
【答】市田柿
【新潟】あられやさんのうっかりから偶然できたお菓子ですが、子どものおやつとしても大人のおつまみとしても美味しい一品。
【ヒント】あられを作っている小判形の型を踏んで歪めてしまい、ゆがんだ型をそのまま使って作ったあられがあるものに似ていました。
【答】柿の種
【富山】淡雪羹を乾燥させた表面に、みりんなどで味を付けた卵黄をつけて焼き上げたお菓子。見た目は卵焼きのようです。
おわら風の盆という行事で知られる八尾町(やつおまち)発祥なので「おわら~」という名前です。
【答】おわら玉天
【石川】小判が反ったような形で、柴を積んで川を行く舟を模しているそう。しょうが汁と砂糖を丁寧に塗ってあり雪が積もったような見た目です。
名前は柴を積んだ舟ということで・・・
【答】しばふね
【福井】餅粉を蒸して砂糖、水あめを加えて練ったお菓子。繊維業の盛んだった福井県の最高級絹織物の名前をつけてあります。
【答】羽二重餅(はぶたえもち)
【静岡】浜名湖周辺はこれの養殖がさかんです。このお菓子にはそのエキスが練り込んであるのでこの名前がついています。「~パイ」です。
【答】うなぎパイ
【岐阜】長良川の鮎をイメージしたお菓子。求肥をカステラ生地で包んで鮎の顔を焼き付けてある見た目にもかわいいお菓子です。
【答】鮎菓子
【愛知】米粉に砂糖や湯水を加えて練って蒸して作ります。ぱっと見羊羹に似ています。漢字で書くと読みが難しいです。
【答】外郎(ういろう)
【三重】三重県といえば伊勢のこれ。300年の歴史を誇るそうです。
餅の上にこし餡を乗せてあります。
名前は「赤心慶福」という言葉から2文字取りました。
【答】赤福
【京都】焼いてあるのが本来のものだそうです。形は橋や箏を模しているとも言われており、それが名前の由来と思われます。
派生商品として、「生~」があり、米粉、砂糖、ニッキを混ぜて蒸したもので、餡をはさんであるものもあります。
【答】八つ橋
【大阪】お米を原料に作ったおこし。通常の粟おこしと違って隙間がないのでかなり固いです。名前はその固さから来ています。
【答】岩おこし
【滋賀】小豆餡に小麦粉または上新粉を混ぜて蒸して作った羊羹です。竹の皮で包んであるのが特徴。
名前の由来は諸説ありますが、丁稚(でっち)が帰省したお土産としてこの羊羹を作って持って行ったなどと言われます。
【答】丁稚羊羹
【兵庫】ウエハースのようなさくさくの薄焼き生地でバニラやチョコ、いちごなどのクリームを挟んだお菓子です。
名前はワッフルという意味のフランス語です。
【答】ゴーフル
【奈良】マメ科の植物から作る餅で、透明でツルツルもちもちしています。
お好みできな粉や黒蜜をかけて食べます。
名前は材料の植物の名前が付いています。
【答】葛餅
【和歌山】参勤交代の時の携行食にされていたという酒饅頭。ふっくらもちもちの食感が特徴です。
名前の由来は、饅頭の上に「本」の字が焼き付けてあること。
【答】本の字饅頭
【広島】餡をカステラ生地で包んだお菓子で、日本三景の宮島のある植物の葉の形をしています。
かつて漫才ブームの折、B&Bのギャグにもなりました。
【答】もみじ饅頭
【岡山】桃太郎が配った団子です。
【答】きびだんご
【鳥取】黒糖と和三盆のやさしい味わいのお饅頭。
形が特徴的で名前の由来にもなっています。
お店の名前から別名「おたふく饅頭」とも言います。
【答】ふろしき饅頭
【島根】求肥に薄緑色の寒梅粉(かんばいこ)をまぶしたお菓子。
出雲松江藩藩主の松平治郷(はるさと)が考案したとされ、名前の由来も治郷の詠んだ歌から取っていますが、薄緑色の見た目も名前をよく表しています。
【答】若草
【山口】名古屋と同じですが、名古屋が米粉と砂糖を使うのに対して、山口県はわらび粉を使っているのでプルプルしてなめらか。
【答】外郎(ういろう)
【徳島】もち米とうるち米を炊いて米粒が残る程度にすりつぶし、餡を包みます。おはぎに似ていますが、名前にびっくりします。
米を半分残る程度にすりつぶすことが名前の由来とされています。
「半~」です。
【答】半ごろし
米を全部すりつぶしたら「みなごろし」と呼ぶそうです。
【香川】金毘羅さんで有名な香川県のお饅頭で、名前の由来は形がお灸に似ているからだそうです。中には黄身餡が入っています。
【答】灸まん
【愛媛】カステラ生地で餡を巻いてロールケーキのようにしたお菓子。
江戸時代、藩主であった松平定行がポルトガルのお菓子にハマって製法を持ち帰ったそうです。ポルトガルのはカステラ生地でジャムを巻いていたそうですが、餡にほんのり柚子を香らせることで見事な和菓子になりました。
【答】タルト
【高知】昭和30年頃から作られている高知県民のソウルフード。
実は全国にあるのですが、高知県のは豆を揚げた油を使っているのでおいしさが別格です。少し塩気のあるビスケットで食べ始めるととまらない。
「~ビスケット」といいます。
【答】ミレービスケット
【福岡】黄身餡の入ったお饅頭ですが、ある生き物の姿をしています。
頭から食べるかお尻から食べるか悩んだことがあるはず。
【答】ひよこ
【佐賀】羊羹ですが普通の羊羹と違って外側が砂糖でシャリっと固く、中はやわらかいのが特徴になっています。
作られている地域の名前が入っています。「~羊羹」といいます。
【答】小城羊羹
【大分】練った小麦粉を平たく伸ばし茹でたものに、砂糖やきな粉をまぶして食べるおやつです。
大分出身の村山富市さんが首相に就任した時、全国に知れ渡りました。
【答】やせうま
【長崎】ポルトガルから伝わったお菓子を独自に発展させたお菓子です。
卵を泡立て、小麦粉、水あめを混ぜて生地を作り、オーブンで焼いたものです。さお型(直方体)で片面にザラメ糖がついていたりします。
【答】カステラ
【熊本】サツマイモを小麦粉で作った生地で包み蒸したおやつ。
中に餡も入っていることがあります。
「~団子」といいます。
【答】いきなり団子
【宮崎】宮崎のいろんなお店が作っており、宮崎の定番スイーツになっています。クリームチーズをクッキー生地で包んでいるのがオーソドックスな形ですが、チーズの甘さや生地の感じはお店によって特徴があります。
【答】チーズ饅頭
【鹿児島】砂糖、山芋、水とうるち米から作ったある粉を使って作ります。
白いスポンジのような見た目で食感も軽いです。
元はさお型でしたが、最近は餡などを入れて饅頭として売っていることが多いです。
【答】かるかん
【沖縄】小麦粉、砂糖、ラードを使って作ったクッキーのようなお菓子。
琉球王朝時代からある歴史あるお菓子です。
食べた時ホロホロほどける感じの食感。
【答】ちんすこう
誕生日
●吉永みち子(作家 1950年)
夫は騎手の吉永正人さん。
「気がつけば騎手の女房」という作品があります。
テレビ番組のコメンテーターとしても活躍しています。
●やくみつる(漫画家 1959年)
本業は漫画家で、「がんばれエガワ君」などの作品があります。
博識を活かしてテレビのクイズ番組に出演したり、コメンテーターとしても活躍。
●くまモン(熊本県PRキャラクター)
2011年ゆるキャラグランプリ王者でもあります。
職業 地方公務員(熊本県営業部長)として、いたるところで熊本を猛アピールしています。