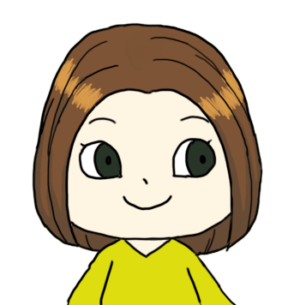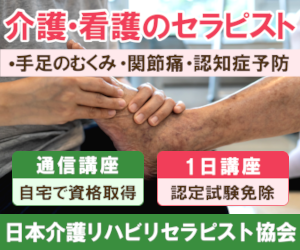冬至
12月22~1月5日頃。
「冬至」というのは一年で最も昼が短く、夜が長い日です。
正午の時の太陽の高さも一年で一番低いです。
ということで、昔の人は太陽の力が弱まる日ととらえていたようです。
【ゆず湯】
冬至といえばゆず湯に浸かります。
「冬至にゆず湯に浸かるとカゼをひかない」という言い伝えがありますね。
ゆずの芳香が邪気やけがれを祓ってくれると考えられていました。
実際ところ、ゆずに含まれる成分が血行促進、湯冷め防止に効果があるそうです。
【カボチャ】
カボチャも冬至の日に食べるとカゼをひかないと言われています。
カボチャは秋から冬の野菜ですが、秋冬は野菜が少ないので、栄養価も高く保存のきくカボチャは重宝されました。
カボチャの黄色には厄を祓うと考えられているそうで、同じく邪気を祓う「小豆」と一緒に煮る「いとこ煮」が冬至の日にはよく食べられています。

なぜ「いとこ」なのか?その名前の由来は
かぼちゃと小豆は茹で時間に差があるので、先に小豆を煮る必要があり、それから時間が経ってカボチャを投入するそうです
つまり、追い(甥)追い(甥)煮る→甥と甥はいとこの関係
など諸説あるそうです。
【冬至粥】
冬至の日には小豆の入った粥を食べて無病息災を祈る風習もあるそうです。
小豆の厄払いパワーですね。
【「ん」がつく食べもの】
冬至の日に「ん」がつく食べものを7種類食べると運がつくと言われています。
うどん、にんじん、ぎんなん、れんこん、寒天、かぼちゃ(南瓜は「なんきん」と呼びます)、金柑、大根、はんぺん・・・
「ん」のつく食べ物を7つあげてみましょう!
【一陽来復】
冬至の別名です。
意味は「冬が去って春が来る」とか、「凶事続きのあとにようやく運が向いてくる」といった意味だそうです。
昼の一番短い冬至の次の日からは、また日が少しずつ長くなっていくことから、「再生」「復活」というような思いがあったのかもしれませんね。
七十二候
二十四節気冬至の候は以下の3つです。
初候: 乃東生ず(なつかれくさしょうず)

12月22~26日頃。
「なつかれくさ」というのはウツボグサのことです。
ウツボグサは夏の始まりに紫の花をつけますが、夏の盛りには枯れてしまいます。
そして、冬になり本来緑の少なくなったこの頃に芽を出します。
他の多くの植物とは逆ですね。
夏至の初候である「乃東枯る」とは対の関係をなしています。
次候: 麋角解つる(しかのつのおつる)

12月27~31日頃。
「麋(しか)」とは、ヘラジカなどの大型の鹿のことを指しているそうです。
この時期になると、オスの角が生え変わりのため自然と抜け落ちるそうです。
末候: 雪下麦を出だす(せっかむぎをいだす)

1月1~5日頃。
一年の最初の七十二候です。
一面の雪景色の下では、早くも麦が芽を出していますよという意味です。
麦は地域によって違いがありますが、9~11月頃種まきし、5~8月頃収穫します。
その間に「麦踏み」が行われます。
麦踏みというのは、生えてきた麦を足で踏んづけること。
こうすることで、根が張りとれる実の量も増えるそうです。