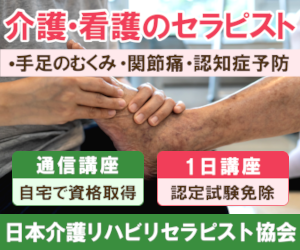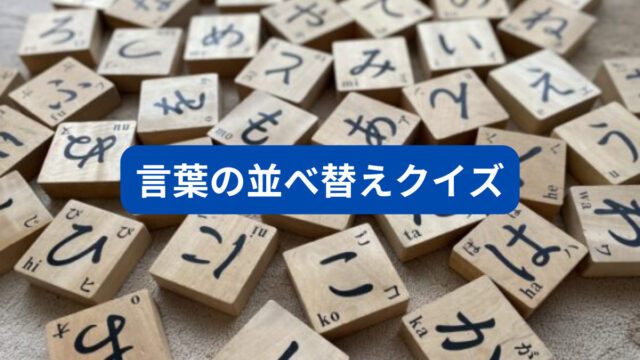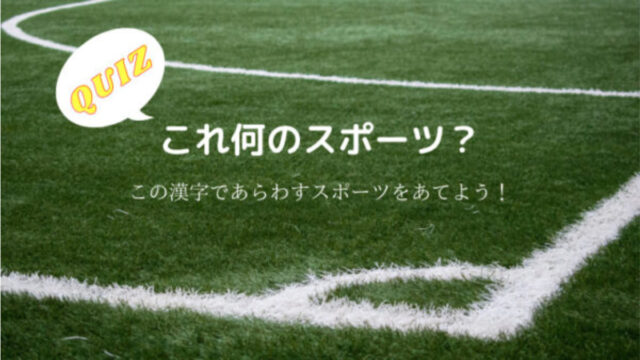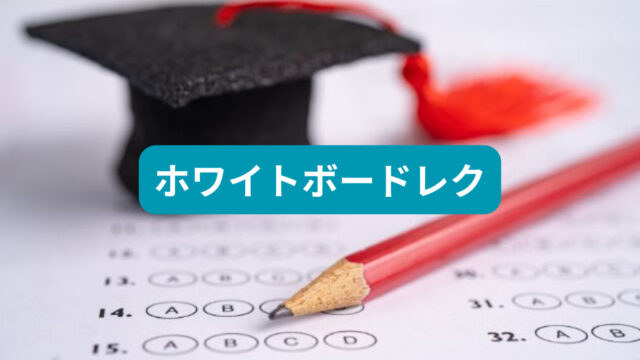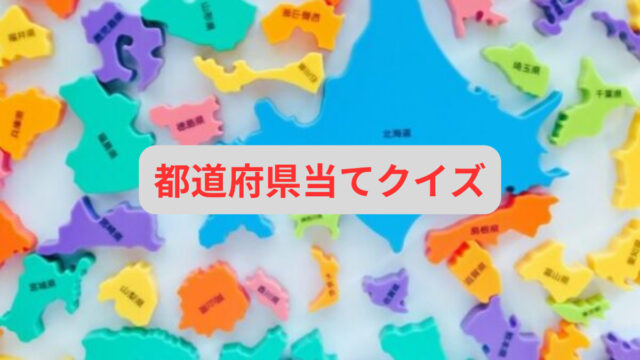スポンサーリンク

高齢者施設のホワイトボードレクで使えることわざ、慣用句、故事成語を集めました。
(注:ことわざ、慣用句、故事成語をまとめて「ことわざ」と表記します。)
ことわざって、普段の会話などでも使ったりするので馴染み深いし、脳トレにはおすすめです。
Contents
スポンサーリンク
ことわざクイズのやり方
- 司会者がことわざの意味を言って、利用者さんがことわざを答える
- 司会者が意味を言って、利用者さんがことわざを答える
①の方が、難易度も低く、司会者のヒントも出しやすいと思います。
②は、ホワイトボードに「○○に小判」という風に虫食いにして書くと答えやすいと思います。
また最初に、「動物の出ることわざクイズをしますよ」というようにジャンルをお知らせすると、それが大きなヒントになって問題が解きやすいです。
ホワイトボードレクの進め方のポイントについてはこちらをどうぞ

【デイサービス】盛り上がるホワイトボードレク28選【高齢者レクリエーション】デイサービスなど高齢者施設では欠かせないホワイトボードレク。
脳トレ効果や、利用者さん同士のコミュニケーションなどの効果が期待できます。
介護職の方向けにホワイトボードレクのアイデアや、メリット、盛り上げるポイントなどを書いています。
...
ことわざクイズのネタ
動物の入ったことわざ

※表中太字で書いているところは、ヒントや話を広げるきっかけになる声掛けの例です。
難易度:低
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| カエルの子はカエル | 子どもは結局は親に似ているという意味 親に似た道に進むという意味合いで使われることが多い |
| トビがタカを生む | カエルの子はカエルの逆で、凡人の親から優れた子どもが生まれること |
| 犬も歩けば棒にあたる | 何か行動することで、思わぬ幸運に恵まれること (最近幸運なことがありましたか?) |
| 馬の耳に念仏 | 馬に念仏を聞かせても無駄なように、意見や忠告を聞き入れないこと |
| 亀の甲より年の功 | 年長者の意見や知恵が深いことの例え (ヒント:まさにご利用者さまのことです) |
| カラスの行水 | よく体を洗わず入浴時間が短い人のこと |
| 鶴は千年、亀は万年 | 長寿でおめでたいこと |
| 捕らぬ狸の皮算用 | まだ手に入っていないのに、計画を立てること (ヒント:宝くじを当たった気になって世界一周とか妄想してしまいますが、そんな状態のこと) (利用者さんも取らぬ狸を皮算用した経験ありますか?) |
| 猫に小判 | どんなに価値あるものでも、それが分からないものには何の役にも立たないこと、反応がないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:豚に真珠、馬の耳に念仏 |
| 河童の川流れ | 泳ぎ上手な河童ですらたまには川に流されるということから、その道の達人でもたまには失敗するというたとえ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:猿も木から落ちる、弘法にも筆の誤り |
| 二兎を追う者は一兎をも得ず | 一度に二つのものを得ようとして、結局は一つも得ることができないこと 欲張ってはだめということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:虻蜂(あぶはち)取らず (反対の意味にあたることわざを知っていますか?) 答:一石二鳥、一挙両得 |
| 能ある鷹は爪を隠す | 才能がある人は、普段はそれを見せびらかすことはせず、隠していること (実は私も隠してる才能ありますという方いますか?隠れた特技、面白い特技など教えてください) |
| 蓼(たで)食う虫も好き好き | 蓼というのは葉の辛い植物で、これを好んで食べる虫がいるように、好みは人それぞれということ 物好きな人のこと |
| 飛んで火にいる夏の虫 | 夏の虫が火に飛び込んで死ぬように、自分から危険なところに首を突っ込んでいくような愚かな人のこと (ヒント:時代劇でよく使われることわざです) |
| 鳶に油揚げをさらわれる | トンビがサッと降りてきて油揚げをかっさらって行くように、あっという間に大事なものを取られてしまうこと |
| 猫糞(ねこばば) | 拾ったお金などをこっそり自分のものにすること ばばって糞、つまりウンチのことですね 猫が自分の糞を足で砂をかけて隠すことが由来です (漢字の読みを当ててほしい 「ねこふん」「ねこぐそ」と読んでしまいそうです) |
| 泣き面に蜂 | 泣いているところにさらに蜂が指して、不幸に不幸が重なること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:弱り目に祟り目 |
| 俎板(まないた)の鯉 | まな板の上に乗せられた鯉は、もうどうされようと自分ではどうしようもないことから、人の意のままになるより他にどうしようもない状態のことを指します。 |
| 猫の手も借りたい | 役に立たない猫の手すら借りたいほど、とにかく忙しい状態のこと |
| 虎の尾を踏む | ものすごく危険なことをすること |
| 犬猿の仲 | とても仲が悪いこと |

難易度:中
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 立つ鳥跡を濁さず | 鳥の飛び立った跡は水が濁らずきれいなことから、人も去る時は後をきちんとするようにといういましめ |
| エビで鯛を釣る | エビのように小さいもので鯛のような大きいものを釣る つまり小さな元手で大きな利益をえること |
| 鴨が葱(ねぎ)を背負って来る | 都合のよいことが重なり、ますますよくなる状態になること 「カモネギ」と言って、カモがネギを背負ってきてくれたおかげで、いっぺんにカモ鍋の材料がそろってラッキーという状態 |
| 窮鼠(きゅうそ)猫を嚙む | 弱いものでも追い詰められたら、必死になって強いものに反撃し苦しめることがあること |
| 雀百まで踊り忘れず | 人は幼い時に見つけた習慣を、歳を取ってもなかなか直すことができないことのたとえ (なかなか直せない習慣やクセとかありますか?) (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:三つ子の魂百まで |
| 藪をつついて蛇を出す | 余計なことをしたばかりに災難に遭うこと (略して) 答:やぶへび |
| 磯の鮑(あわび)の片思い | 鮑は二枚貝の片方の貝殻しかないような見た目をしていることから |
| 蛞蝓(なめくじ)に塩 | なめくじに塩をかけると縮むことから、苦手なものが出たとたんに縮こまって元気がなくなること |
| 一寸の虫にも五分の魂 | 小さな弱い存在の者にも意地や考えがあるので侮ってはいけないというたとえ |
| 腐っても鯛 | 本当に良いものというのは、多少時期を過ぎても価値が失われないこと |
| 蛇足(だそく) | 余計なものこと 余計なものを足して台無しにしてしまうこと |
| 飛ぶ鳥を落とす勢い | ものすごく勢いのある者や勢力のこと 勢いある権力者などに使います |
| 虎の威を借る狐 | 自分はなんの力もないのに、力のある人にくっついて威張ったり好き勝手する人 |
| 猫に木天蓼(またたび) | 大好物のこと (漢字を書いて読みを当ててもらうこともできますね) |
| 鳩が豆鉄砲を食ったよう | びっくりして目を丸くすること |
| 虎穴に入らずんば虎子を得ず | 大きな利益や成果を得るためには危険を冒す必要があること |
| 天高く馬肥ゆ | 空が高く、馬がたくさん草を食べ太る季節 秋の豊さをたたえる表現 |
| 鰯(いわし)の頭も信心から | イワシの頭のように何の価値もないようなものでも、信心がある人から見れば有難く価値あるものになること |
難易度:高
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 雉も鳴かずば撃たれまい | 余計なことを言ったばかりに災いに合うこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:口は禍(わざわい)の元 |
| 窮鳥(きゅうちょう)懐に入れば猟師も殺さず | 窮地に陥った人が助けを求めてくれば、これを助けるべきということ または窮地に陥った人は敵にさえも助けを求めるということ |
| 水魚の交わり | 水と魚の関係のように切っても切れない友情のこと |
| 烏合の衆 | カラスが集まったように、ただ集まっただけで統制が取れていない集団のこと |
| 梅に鶯(うぐいす) | 似合うことの例え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?ヒントは花札ですよ) 答:松に鶴、紅葉に鹿、牡丹に燕 |
| 鵜(う)の目鷹の目 | 鵜や鷹が目つき鋭く獲物を探すように、真剣にものごとを見る様子 |
| 同じ穴の狢(むじな) | 一見別のものに見えても、実は同じであること 同じ利害関係にいる悪仲間という意味で使われます (狢って何の動物でしょうか) 答:たぬき |
| 胡蝶(こちょう)の夢 | 人生が夢のようにはかないこと (胡蝶って何の動物でしょうか) 答:蝶 美しく表現したら胡蝶になります |
| 獅子身中の虫 | 内部の者でありながら、その内部に災いをもたらすもののこと (獅子って何の動物でしょうか) 答:ライオン |
| とどのつまり | 結局のところという意味 (とどってどんな動物ですか) 答:魚のボラのことです 出世魚でボラのあと最後がとどになるため ※アシカの仲間のトドではないですよ |
| 馬脚を露(あらわ)す | 隠していた本性がばれること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:化けの皮が剝がれる、尻尾を出す |
| 鶏口(けいこう)となるも牛後(ぎゅうご)となるなかれ | 大きな組織の末端にいるより、小さな組織のトップになる方がいいということ 鶏口は鳥のくちばし、牛後は牛のお尻のこと (同じ意味で四字熟語になっています) 答:鶏口牛後 |
| 鹿を追う者は山を見ず | ひとつのことに夢中になり過ぎて周りの状況が見えなくなっている様子 |
| 塞翁(さいおう)が馬 | 思いがけないことが幸せにつながったり不幸につながったりことから、先は予測がつかず、いちいち喜んだり悲しんだりしないようにというおしえ 「人間万事塞翁が馬」ともいいます。 塞翁というのは中国に住んでいたおじいさんで、そのおじいさんの飼っていた馬がある日逃げて行ってしまいました(不幸)。ところが後日別の良い馬を連れて戻りました(幸)。しかし今度は塞翁の息子が馬に乗っていて落馬しケガ(不幸)をしてしまいます。でも息子はこのケガのお陰で、戦争に行かなくてよくなり死なずに済みました(幸)。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:禍福(かふく)は糾(あざな)える縄の如し |
| 虎の子 | 大切に持ち続けて手放さないもの。秘蔵の品のこと。 |
| 魚の水を得たるが如し | その人にふさわしい場所を見つけ大活躍すること。 |
数字の入ったことわざ
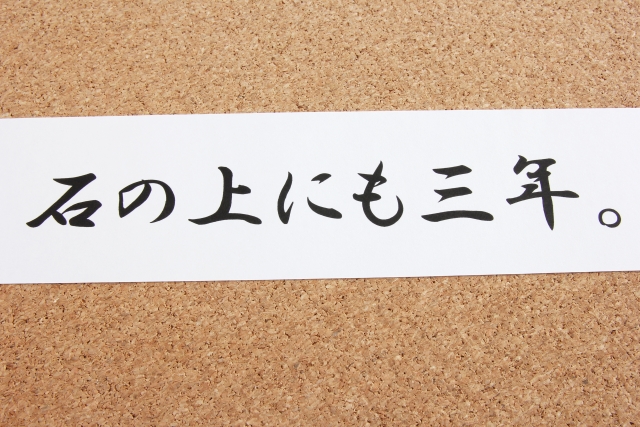
難易度:低
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 親の七光り | 親の知名度によって、本人にこれといって才能がなくても取り立てられたり得をすること |
| 海千山千 | 経験豊富でぬかりない人のこと |
| なくて七癖 | 誰でも人は多かれ少なかれ癖をもっているということ (なくて七癖は一部です。全体を言えますか) 答:なくて七癖、あって四十八癖 癖が少なそうな人でも七つくらい、多い人は四十八癖持っているという意味 |
| 二足の草鞋(わらじ)を履く | 二種類の仕事を一人で掛け持ちする人のこと |
| 盗人にも三分(さんぶ)の理(り) | どんなことにも、もっともらしい理屈がつけられること |
| 人を呪わば穴二つ | 人に被害を与えたら、いつか自分にも跳ね返ってくるという意味 穴二つとは、呪った相手と自分自身の墓穴のことを言っています。 |
| 石の上にも三年 | 冷たい石の上に三年も座れば温まるもの つらいことや苦しいことも辛抱して耐えることが大切という教え |
| 三度目の正直 | 一度目、二度目がうまくいかなくても三度目にもなればうまくいくこと |
| 七転び八起き | 何度失敗してもくじけず立ち直ること |
| ローマは一日にして成らず | なにか大きなことを成すには、短期間ではできず、長い年月と労力を要するということ。 |
| 風邪は万病のもと | 風邪をひくと抵抗力が弱くなるので、他の病気にもかかりやすいことから、風邪をみくびってはいけない |
| 酒は百薬の長 | お酒は適量であれば、どんな薬にも勝るお薬になること |
| 早起きは三文の徳 | 早起きすると何かしら得があるということ。 |
| 一度あることは二度ある | 良いことも悪いことも、一度起きたことは、もう一度起こりがち 特に悪いことのときは気を付けようという教え (そんな経験のある方はいらっしゃいますか) |
| 二度あることは三度ある | 一度あることは~と同じで二度あると三度目もあるということ。 |
| 一寸先は闇 | 真っ暗闇では前が全く分からないように、先のことは何が起こるか予測できないこと。 |
| 天は二物を与えず | どんなに優れたような人にも欠点はあるということ 天はひとりの人間に、そんないくつも優れたものを与えてはくれないということ |
| 二階から目薬 | 二階から一階にいる人に目薬を差そうとする行為のように、まわりくどくて効果のないことの例え |
| 九死に一生を得る | 到底助からないような状況から、かろうじて助かること 死ぬ確率:生きる確率=9:1という意味 |
| 三人寄れば文殊の知恵 | 普通の人でも三人集まれば、文殊菩薩のように良い知恵が出てくるという意味 |
| 二兎を追う者は一兎をも得ず | 一度に二つのものを得ようとして、結局は一つも得ることができないこと 欲張ってはだめということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:虻蜂(あぶはち)取らず (反対の意味にあたることわざを知っていますか?) 答:一石二鳥、一挙両得 |
| 鶴は千年亀は万年 | 長寿でおめでたいこと |
| 人の噂も七十五日 | 人がうわさ話をするのも一時的なもので長続きはしない(七十五日もすれば忘れられる) |
| 三つ子の魂百まで | 子どもの時の性格などは一生変わらないこと。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:雀百まで踊り忘れず |
| 八方ふさがり | どっちを向いても行き詰っている状態 |
| 桃栗三年柿八年 | 芽が出て実がなるのに桃、栗は三年かかり、柿は八年かかるということ それだけ辛抱強くいなければいけないという教え (この続きが分かる方はいますか) 答:梅は酸(す)いとて十三年、柚(ゆず)は九年の花盛り、びわは九年でなりかねる |
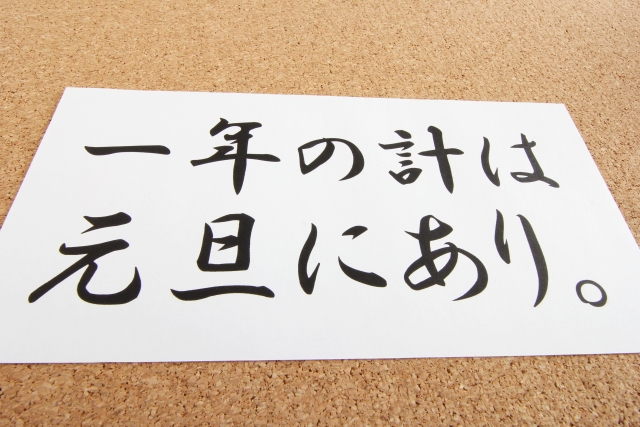
難易度:中
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 女三人寄れば姦(かしま)しい | 女性が三人も集まればうるさいくらい賑やかであること 姦しいの漢字が女を三つ集めたものからきています。 |
| 鬼も十八、番茶も出花 | 器量がいまいちの娘でも十八歳くらいのお年頃になれば、それなりの魅力が出てくること 番茶はあまりいいお茶ではないけれど、いれたての時くらいはいい香りがすることが由来です |
| 悪事千里を行く | 悪いことはあっという間に広まる 良いことはなかなか広がらないのに、悪いことはすぐに広がる |
| 千里の道も一歩より | どんな大きなものごとも、小さなひとつひとつの積み重ねから始まるということ |
| 一事が万事 | ひとつの事をみれば、他のすべての事も予測がつくこと 悪い一面を見て、他のすべてもダメだろうというような悪いことに使うことが多いです |
| 一難去ってまた一難 | 一度難を逃れても、次から次へと災難が襲ってくること。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:虎口を逃れて竜穴に入る、前門の虎後門の狼 |
| 一日の計は朝にあり 一年の計は元旦にあり | その日一日の計画はその日の朝に、その年一年の計画は元日にというように、何事も早め早めに計画すること。 |
| 一寸の虫にも五分の魂 | 小さな弱い存在の者にも意地や考えがあるので侮ってはいけないというたとえ |
| 五十歩百歩 | 似たり寄ったりで大差ないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:団栗(どんぐり)の背比べ、目糞鼻糞を笑う、大同小異 |
| 雀百まで踊り忘れず | 人は幼い時に見つけた習慣を、歳を取ってもなかなか直すことができないことのたとえ (なかなか直せない習慣やクセとかありますか?) |
| 二の舞を演じる | 前の人と同じ失敗をすること。 |
| 口八丁手八丁 | しゃべりも仕事も達者なこと。 |
| 当たるも八卦当たらぬも八卦 | 占いは当たったり外れたりするものなので、あまり気にしてはいけないという教え |
難易度:高
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 五臓六腑に染み渡る | 五臓六腑とはお腹、ひいては体の中全体に染み渡るということ。 お酒とか飲んだ時言いますね。 |
| 腹に一物(いちもつ) | なにか企みをもっていること。 |
| 明日の百より今日の五十 | 不確かな未来のことより、今日確かに手に出来るものが当てにできるということ |
| 一を聞いて十を知る | ひとつのことを聞いてすべてを理解すること ものわかりのいい、聡明なこと |
| 七重の膝を八重に折る | お詫びや依頼をする様子が非常に丁寧な様子。 |
| 三顧の礼 | 三顧というのは三度訪れるということです。 目上の人が、仕事を引き受けてもらうのに何度も足を運んで礼を尽くすこと。 中国の蜀(しょく)の国の劉備(りゅうび)が諸葛孔明(しょかつこうめい)に軍師になってもらうため三度訪ねたという故事からなっています。 (この物語のタイトルはなんでしょう) 答:三国志 |
| 三十六計逃げるに如かず | 追い込まれたときは、逃げるのも作戦の内で、さっさと逃げるのが良いという教え。 (三十六計って何ですか?) 答:中国の兵法で三十六種あったそうです。 |
| 岡目八目 | 何かをしている本人より周りの人の方が冷静に見て正しい判断ができること |
| 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥 | 知らないことを聞くのは一時だけの恥だが、聞かずに過ごすと無知のまま一生の恥をさらすという意味 恥ずかしがらずに分からないことは訪ねようという意味。 |
| 百害あって一利なし | 害ばかりで、利点がまったくないこと。 |
家族、世の中、人との関わにまつわることわざ

難易度:低
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 秋なすは嫁に食わすな | ①秋なすは美味しいので嫁に食わせるのはもったいない ②秋なすは体を冷やす、または種が少ないので子種が少なくなるので嫁に食べさせてはいけない 以上、二つの説があります。 |
| かわいい子には旅をさせよ | 子どもはかわいいが、かわいいからこそ将来のことを考えて、敢えて世間に出して辛さや苦しさ味わわせた方がよい。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:獅子の子落とし |
| 子は鎹(かすがい) | かすがいというのは材木をつなぎ合わせる金具のことですが、子どもがそれと同じように夫婦をつなぎとめる役割を果たしているという意味。 |
| 泣く子は育つ | 大きな声で泣く子は元気があるので、丈夫に育つという意味。 |
| 夫婦喧嘩は犬も食わぬ | 夫婦喧嘩は大した原因で起こることが多く、かつ放っておいてもいつの間にか仲良くなっているから、周りがいちいち仲裁する必要のあるものでもない。 |
| ああ言えばこう言う | 人の言うことを素直に聞かずに、なんやかんやと文句を言う人の事 |
| 住めば都 | どんなに不便なところでも住んでいく間に愛着もわき、都のように良く感じること |
| 捨てる神あれば拾う神あり | 世の中では、人に見捨てられてしまうこともあるが、反対に手助けをしてくれる人もいるので、くよくよしてはいけないという教え |
| 袖すり合うも他生(たしょう)の縁 | 道で他人と袖がふれ合うような些細な出来事も、前世からの因縁によるものだから、人との出会いを大切にするようにという教え 他生とは、多生とも書きますが、前世のことを指しています |
| 竹馬(ちくば)の友 | 幼いころ一緒に竹馬で遊んだような幼馴染のこと。 (みなさんにも竹馬の友はいますか?) |
| 出る杭は打たれる | 才能のある人は目立ってしまい、周りの人からねたまれたり、憎まれたりすること。でしゃばって周りから責められたりすること |
| 敵に塩を送る | たとえライバルであっても、相手が困っているときは助け船を出すこと。 (このことわざの由来が分かる人はいますか?) 答:戦国時代、武田信玄が塩が手に入らずに困っていたところ、ライバルの上杉謙信が塩を送って助けたという逸話 |
| 手塩に掛ける | 自分の手で世話して大切に育てること。 |
| 情けは人の為ならず | 人にかけた情けはいずれ回りまわって自分に返って来るということ。だから自分のためである。 ※人に情けをかけるのは、その人にとって為にならないという解釈は誤りです。 |
| 憎まれっ子世に憚(はばか)る | 人に嫌われがちな人間に限って世の中で幅をきかせているものである。 はばかるとは、幅をきかせることです。 |
| 人は見かけによらぬもの | 人の見かけだけでは、その人の本当のことは分からない。 見た目と中身は違うことが多く、意外な一面があること。 (人は見かけによらなかったエピソードはありますか?) |
| 人のふり見て我がふり直せ | 人の行動などを見て、自分の悪い所を直すよう心掛けなさいという教え。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:他山の石 |
| 焼け木杭(ぼっくい)に火がつく | 一度消えたように見えた燃えさしが、また燃え出すことがあるように、別れた男女の仲も、ちょっとしたきっかけでまた元に戻りやすいこと |
| 類は友を呼ぶ | 気の合う者同士は自然と寄り集まり仲間になること。 |
難易度:中
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| お前百までわしゃ九十九まで | 夫婦共に長生きしていこうという願いが込められています (この続き分かりますか) 答:ともに白髪の生えるまで |
| 女房と畳は新しいほうがよい | 新しいものは何にしても気持ちがいいものだという意味 (反対の意味にあたることわざを知っていますか?) 女房と味噌は古いほどよい |
| 酸いも甘いも嚙み分ける | 人生経験豊かで、世の中や人間の裏や表も知り尽くしていること (利用者のみなさんはまさにこれですね) |
| 旅は道連れ世は情け | 旅に出る時は誰かと一緒が心強いように、世の中もお互い助け合っていくのが大切であるという教え |
| 遠い親戚より近くの他人 | 遠くに住んでいる親戚の人より、近くに住んでいる他人の方が頼りになること |
| 遠くて近きは男女の仲 | 遠く離れて縁遠く見えても、男女は意外に結ばれやすいこと |
| 人の口に戸は立てられぬ | 人の口を戸を閉めるように閉じることはできないように、噂話は防ぎようがないということ |
| 火のない所に煙は立たぬ | 火種がなくては火はおきないので、根拠があるからこそ噂も立つものである |
| 渡る世間に鬼はない | 世の中は辛いことも多く、鬼のように冷たい人間もいるが、逆に心優しい人もいるという教え。 (このことわざに似たタイトルの有名なドラマがあります。さて何でしょう? ヒントは泉ピン子さん) 答:渡る世間は鬼ばかり |

難易度:高
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 糟糠(そうこう)の妻 | 糟はさけかす、糠はぬかの意味。つまり粗末な食べ物を食べていた貧しかった頃から長年連れ添った妻のこと |
| 阿吽(あうん)の呼吸 | 阿は吐く息のこと、吽は吸う息の事。互いの調子などがぴたりと合うこと。 |
| 東(あずま)男に京女 | 関東の男性と、京都の女性がお似合いの組み合わせという意味。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:伊勢男に筑紫女、越後女に上州男 |
| 縁は異なもの味なもの | 男女の縁はどこでどう結びつくか、常識や理屈では想像できない不思議なものである。 (ご自分の大恋愛話を披露してもいいよって方いますか?) ※割と女性利用者さんに恋バナ好きがいます |
| 亭主の好きな赤烏帽子 | 一家の主の好みには、家族は従わなければならないという教え 烏帽子というのは普通黒色ですが、亭主が赤烏帽子が好きと言えば家族もそれに従わなければならないというもの。 |
| 居候、三杯目にはそっと出し | 居候は人のうちにお世話になっているので、ご飯の三杯目のおかわりもつい、遠慮してそっとお茶碗を出すという川柳が由来です。 |
| 臭い物に蓋をする | 不正など悪いことを人にばれないように、一時しのぎで隠すこと |
| 道理百遍(ひゃっぺん)、義理一遍 | 道理をどれだけ話しても、たった一度の義理固い行為の方が相手の心を動かすという教え。 |
| 泣く子と地頭には勝てぬ | 理屈が通らないもの(泣く子)と権力のある者(地頭)にはかなわないので、争っても無駄である。 地頭というのは、中世の頃のお役人のことです。 |
| 人の褌(ふんどし)で相撲を取る | 他人のものを利用して自分の役に立てること。自分の目的を果たそうとすること。 |
| 惚れた欲目 | 好きな人のことは、実際のその人より良く見えてしまうこと。欠点ですら良く見えてしまうこと。 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:あばたもえくぼ |
| 楽あれば苦あり、苦あれば楽あり | 楽があればその後には苦があり、苦の後にはまた楽があるということ。 なので、苦しい時も頑張って耐えれば楽しみがあり、逆に楽ばかりでは後に苦労するという教え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:楽は苦の種、苦は楽の種 |
五十音別ことわざ
「ア」から始まることわざクイズです。といった形にすると利用者さんも答えが出やすいと思います。
ア行
アから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| ああ言えばこう言う | 人の言うことに、いちいち言い返して素直に従わないこと |
| 阿吽の呼吸 | 阿は吐く息のこと、吽は吸う息の事。互いの調子などがぴたりと合うこと |
| 青菜に塩 | 打ちひしがれている様子 (ヒントは、実際に青菜に塩を振ったらどうなりますか?) (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:なめくじに塩 |
| 青は藍より出でて藍より青し | 弟子が師匠を超えてしまうこと 青色は藍から取りますが、もとの藍より青い色がでることが由来 |
| 秋なすは嫁に食わすな | ①秋なすは美味しいので嫁に食わせるのはもったいない ②秋なすは体を冷やす、または種が少ないので子種が少なくなるので嫁に食べさせてはいけない 以上、二つの説があります |
| 秋の日はつるべ落とし | 秋は日が沈むのが早いことのたとえ 井戸につるべを落とすように陽が沈んでしまうから |
| 悪事千里を行く | 悪いことはあっという間に広まる 良いことはなかなか広がらないのに、悪いことはすぐに広がる |
| 悪銭身に付かず | 悪いことをして得たお金は、つまらないことに浪費してすぐに無くなってしまうこと |
| 足下(あしもと)を見る | 相手の弱みに付け込んで自分の利益をはかること |
| 頭隠して尻隠さず | 悪事や欠点などの一部を隠しただけで、すべて隠せたつもりでいること |
| 後の祭り | 手遅れになること また、それを後悔しても遅いこと |
| 後は野となれ山となれ | 自分のやるべきことはやってしまったので、後は運に任せてどうとでもなれということ |
| 油を売る | 長話や無駄話などをして仕事を怠けること |
| 雨降って地固まる | いやなこと、もめ事などが時間が経って、良い結果に落ち着くこと |
| 案ずるより産むが易し | 事前にいろいろと心配していても、意外に大事もなく心配するほどのことでもなかったこと |
| 明日の百より今日の五十 | 不確かな未来のことより、今日確かに手に出来るものが当てにできるということ。 |
| 東(あずま)男に京女 | 関東の男性と、京都の女性がお似合いの組み合わせという意味 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:伊勢男に筑紫女、越後女に上州男 |
| 当たるも八卦当たらぬも八卦 | 占いは当たったり外れたりするものなので、あまり気にしてはいけないという教え |
| 雨だれ石を穿(うが)つ | 小さな雨だれでも、長い時間をかけて同じ場所に落ち続けたら、かたい石にすら穴をあけてしまう 同じように、小さな努力も地道に続けていくことでいつか必ず実を結ぶという教え |
| 嵐の前の静けさ | 嵐の前に静かな状態の時があるように、なにか大事件が起こる前に静けさがあること |
イから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 言うは易く行うは難し | 口で言うのは簡単でも、それを行動に移すのは難しいこと |
| 生き馬の目を抜く | 生きている馬の目を抜き取るほど、すばしこく抜け目ないこと |
| 石に漱(くちすす)ぎ流れに枕す | 負け惜しみの強いこと こじつけ、屁理屈を通そうとすること 漱ぐというのは、うがいすることです 本当は「石に枕し、流れに漱ぐ」というべきなのに、言い間違いした中国の孫楚(そんそ)という人物が、「石に漱ぐのは、歯磨きするためで、水の流れを枕にするのは耳を洗うため」とうまいことこじつけたことが由来です (この故事からできた言葉と、この言葉からヒントを得て自分のペンネームをつけた明治文豪はだれでしょうか) 答:流石(さすが)、夏目漱石 |
| 石の上にも三年 | 冷たい石の上に三年も座れば温まるもの つらいことや苦しいことも辛抱して耐えることが大切という教え |
| 石橋を叩いて渡る | 用心の上に用心を重ねる様子 固い石橋すら壊れるかもと心配して叩きながら渡るという意味 (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:念には念を入れよ |
| 医者の不養生 | 医者が患者には不摂生を戒めながら、いざ自分のことになると不摂生していること 口で言いながら実行が伴わないことを指します (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:紺屋(こうや)の白袴(しろばかま) |
| 何れあやめか杜若(かきつばた) | あやめと杜若は似ていますが、どちらも甲乙つけがたいほど美しいということ |
| 急がば回れ | 急ぐときほど落ち着いて、確実にやるほうが成功すること |
| 一事が万事 | ひとつの事をみれば、他のすべての事も予測がつくこと 悪い一面を見て、他のすべてもダメだろうというような悪いことに使うことが多いです |
| 一度あることは二度ある | 良いことも悪いことも、一度起きたことは、もう一度起こりがち 特に悪いことのときは気を付けようという教え (そんな経験のある方はいらっしゃいますか) |
| 一難去ってまた一難 | 一度難を逃れても、次から次へと災難が襲ってくること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:虎口を逃れて竜穴に入る、前門の虎後門の狼 |
| 一を聞いて十を知る | ひとつのことを聞いてすべてを理解すること ものわかりのいい、聡明なこと |
| 一寸先は闇 | 真っ暗闇では前が全く分からないように、先のことは何が起こるか予測できないこと |
| 一寸の虫にも五分の魂 | 小さな弱い存在の者にも意地や考えがあるので侮ってはいけないというたとえ |
| 犬も歩けば棒に当たる | 何か行動することで、思わぬ幸運に恵まれること (最近幸運なことがありましたか?) |
| 井の中の蛙大海を知らず | 小さな井戸の中の蛙は、外の大きな海のことを知らないように、自分の狭い知識にとらわれ、外の広い世界を知らない人のこと |
| 言わぬが花 | 言葉に出して言うよりも黙っている方が味わいがあったりすること |
ウから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 魚心あれば水心 | 相手が好意的であれば、こちらも好意的に接するようになること 相手の出方次第で、こちらにも応じる用意があること |
| 烏合の衆 | カラスが集まったように、ただ集まっただけで統制が取れていない集団のこと |
| 雨後の筍 | 雨の後にたけのこが次々伸びてくるように、物事が次々と起こること |
| 氏より育ち | 家柄、血筋などより育った環境や教育の方がよっぽど大切なこと |
| 嘘も方便 | 時と場合によって、物事を円満に進めるには嘘も必要ということ |
| うだつが上がらぬ | いつまでたっても成功、出世ができないこと |
| 独活(うど)の大木 | ただ体が大きいというだけで、何の役にも立たない人のこと |
| 鵜の目鷹の目 | 鵜や鷹が目つき鋭く獲物を探すように、真剣にものごとを見る様子 |
| 馬の耳に念仏 | 馬に念仏を聞かせても無駄なように、意見や忠告を聞き入れないこと |
| 海千山千 | 経験豊富でぬかりない人のこと |
| 売り言葉に買い言葉 | 相手の言った言葉に対して、こちらも負けずに言い返すこと |
| 噂をすれば影が差す | 人の噂をしていると、その噂の本人が偶然現れたりすること |
| 梅に鶯(うぐいす) | 似合うことの例え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?ヒントは花札ですよ) 答:松に鶴、紅葉に鹿、牡丹に燕 |
エから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 江戸っ子は宵越しの銭は持たぬ | 宵越しの銭というのは、一晩持ち越したお金のこと 江戸っ子は、持っているお金はその日のうちに使うのを粋(すい)としていた |
| 絵に描いた餅 | 絵に描いた餅が食べられないように、ただの想像や話を聞いただけでは何の役にも立たない |
| エビで鯛を釣る | エビのように小さいもので鯛のような大きいものを釣る つまり小さな元手で大きな利益をえること |
| 縁の下の力持ち | 表舞台で活躍する人を陰で支える人のこと |
| 縁は異なもの味なもの | 男女の縁はどこでどう結びつくか、常識や理屈では想像できない不思議なものである。 (ご自分の大恋愛話を披露してもいいよって方いますか?) ※割と女性利用者さんに恋バナ好きがいます |
オから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 驕る平家は久しからず | 栄華をきわめた平家が思い上がって身を滅ぼしたように、地位や財力を手にしても慢心したものは必ず落ちぶれるという教え |
| 岡目八目 | 何かをしている本人より周りの人の方が冷静に見て正しい判断ができること |
| 男は度胸女は愛嬌 | 男にとって大事なのは度胸で、女にとっては愛嬌である (この続きがありますが、さて何でしょう?) 答:坊主はお経 |
| 男やもめに蛆(うじ)がわき女やもめに花が咲く | 妻に先立たれた男性は世話をしてくれる人がいないので、身の回りや家が不潔になっていくが、夫に先立たれた女性は自分に時間がかけられるようになるので、小ぎれいになって華やかになる |
| 同じ穴の狢(むじな) | 一見別のものに見えても、実は同じであること 同じ利害関係にいる悪仲間という意味で使われます (狢って何の動物でしょうか) 答:たぬき |
| 鬼に金棒 | 強い鬼が金棒を持ったらさらに強くなるように、もともと強いものにさらに強いものが加わること |
| 鬼の目にも涙 | 普段は厳しい人が、ふと何かのきっかけで涙を流すことがあるというたとえ |
| 帯に短し襷(たすき)に長し | どっちつかずで使い物にならないもののたとえ |
| 溺れる者は藁(わら)をもつかむ | 困難な状況にある人が、助かりたいばかりになんの頼りにもならないようなものにすがりついて助かろうともがくこと |
| 思い立ったが吉日 | 何かをしようと思い立ったら、あれこれ考えずすぐにとりかかった方が良いということ |
| 親の七光り | 親の知名度によって、本人にこれといって才能がなくても取り立てられたり得をすること |
| 終わりよければすべてよし | 物事は結末がよくなければ、最初や途中が良くてもすべてダメになってしまうこと |
| 女心と秋の空 | 女心は秋の空模様と同じで変わりやすいことのたとえ |
| 恩を仇で返す | 人によくしてもらったのに、恩を返すどころか害を与えること |
| 鬼も十八、番茶も出花 | 器量がいまいちの娘でも十八歳くらいのお年頃になれば、それなりの魅力が出てくること 番茶はあまりいいお茶ではないけれど、いれたての時くらいはいい香りがすることが由来です |
| 親の意見と冷や酒は後できく | 親に意見されてもしばらくは何とも感じないが、冷や酒のように後になってじんわり効いてくること |
カ行
カから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 飼い犬に手を嚙まれる | 普段から目をかけて可愛がっていた者から思わぬ裏切りに合うこと |
| カエルの子はカエル | 子どもは結局は親に似ているという意味 親に似た道に進むという意味合いで使われることが多い |
| 風邪は万病のもと | 風邪をひくと抵抗力が弱くなるので、他の病気にもかかりやすいことから、風邪をみくびってはいけない。 |
| 火中の栗を拾う | 自分の利益にならないので、他人のために危険をおかすこと |
| 勝って兜の緒を締めよ | 戦に勝っても油断してはいけない 何事もうまく行っているときも、油断をせずに用心してすすめという戒め |
| 河童の川流れ | 泳ぎ上手な河童ですらたまには川に流されるということから、その道の達人でもたまには失敗するというたとえ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:猿も木から落ちる、弘法にも筆の誤り |
| 勝てば官軍負ければ賊軍 | 戦いにおいては、正義や道理が勝った側にあることになるということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:力は正義、強いもの勝ち |
| 金の切れ目が縁の切れ目 | お金がある時は親しくても、お金が無くなった途端に人間関係が切れること |
| 金は天下の回り物 | お金というのは留まることなく世の中を渡っているものであるから、今の貧乏を嘆いてはいけないという教え |
| 禍福(かふく)は糾(あざな)える縄の如し | 幸不幸は、ちょうどより合わせて作った縄のように代わる代わる訪れること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:塞翁が馬、沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり |
| 壁に耳あり障子に目あり | ひそひそ話のつもりでも壁に耳を当てて聞いていたり、障子に穴を開けてのぞき見ている者がいるかもしれない つまり、秘密はもれやすいので注意しなければならないという戒め |
| 果報は寝て待て | 幸運を求めてジタバタせずに、するべきことをしたら自然と運が向いてくるのを待てという教え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:待てば海路の日和あり |
| 鴨が葱(ねぎ)を背負って来る | 都合のよいことが重なり、ますますよくなる状態になること 「カモネギ」と言って、カモがネギを背負ってきてくれたおかげで、いっぺんにカモ鍋の材料がそろってラッキーという状態 |
| 亀の甲より年の劫 | 年長者の意見や知恵が深いことの例え (ヒント:まさにご利用者さまのことです) |
| 堪忍袋の緒が切れる | 我慢に我慢をかさねて、ついに限界がきて爆発すること |
| 枯れ木も山の賑わい | あまり役に立たないものでもないよりまし |
キ、クから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 雉も鳴かずば撃たれまい | 余計なことを言ったばかりに災いに合うこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:口は禍(わざわい)の元 |
| 木で鼻をくくる | 頼み事など受けた時、冷たい対応を取ること |
| 木に竹を接ぐ | 木に竹を接ぎ木してもうまくいかないように、二つのものがあまりに違い過ぎて調和がとれなかったり、つじつまが合わないこと |
| 昨日の友は今日の敵 | 人の考えなどは変わりやすく当てにすることができないというたとえ |
| 九死に一生を得る | 到底助からないような状況から、かろうじて助かること 死ぬ確率:生きる確率=9:1という意味 |
| 清水の舞台から飛び降りる | 京都の清水寺の舞台は崖に作られているので、そこから落ちたら命の保証がいように、必死の覚悟で決断、実行すること |
| 木を見て森を見ず | 細かい部分にこだわるあまり、全体が見えないこと |
| 臭い物に蓋をする | 不正など悪いことを人にばれないように、一時しのぎで隠すこと |
| 腐っても鯛 | 本当に良いものというのは、多少時期を過ぎても価値が失われないこと |
| 国破れて山河在り | 戦争で国は滅んでしまったが、自然はそのままの姿で存在すること |
| 苦しい時の神頼み | 普段信仰心の無い人でも、苦しい時は神仏にすがろうとすること 日頃あまり付き合いのないような人に、困ったときだけ頼ろうとすること |
| 君子危うきに近寄らず | 徳の高い人は慎み深いので、危険なものには最初から近づかない |
| 君子豹変す | 徳の高い人は自分の間違いをすぐに改めようとすることから、人が態度をガラリと変えることをいう |
ケから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 鶏口となるも牛後となるなかれ | 大きな組織の末端にいるより、小さな組織のトップになる方がいいということ 鶏口は鳥のくちばし、牛後は牛のお尻のこと (同じ意味で四字熟語になっています) 答:鶏口牛後 |
| 芸は身を助く | 身に付けた芸や技術は、それを仕事として身を立てることもできるし、いざという時は、生計の足しにもできる (何か芸に身を助けられた経験はあります?) |
| 怪我の功名 | ここでいう怪我というのは失敗とかの意味です 失敗したことが、偶然思いもよらなかった良い結果をもたらすこと |
| 下駄を預ける | 自分の関わっていたことの後始末などを他人に任せること |
| 逆鱗に触れる | 自分より目上の人を激怒させること (逆鱗というのはさかさまの鱗のことですが、さて何の鱗でしょう?) 答:龍 龍の顎の下に生えていて、これに触れてしまうと龍が激怒し、触れた相手を殺してしまうそうです |
コから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 光陰矢の如し | 月日の過ぎるのが早いこと 過ぎていった時間は、飛んで行った矢が戻って来ることがないように、元には戻らないから |
| 後悔先に立たず | 住んだことを悔やんでも、もうどうすることも出来ないので、最初によく考えて後悔のないようにせよという教え |
| 郷に入っては郷に従え | 新たな場所に住むようになったら、そこの土地の風習に従った方がよいという教え 住む場所に限らず、会社などの組織も同じ |
| 弘法にも筆の誤り | 達人と言われる人も、たまには失敗することがあるということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:猿も木から落ちる、河童の川流れ |
| 故郷に錦を飾る | 地位や名声、富を手に入れて故郷へ帰ること |
| 転がる石には苔が生えぬ | 転がり続ける石には苔が生えようがないように、体を良く動かす働き者はいつまでも健康であること |
| 転ばぬ先の杖 | 失敗しないように、あらかじめ用心しておくこと |
| 転んでもただは起きぬ | 失敗しても、その中から自分の利益になるものを見つけだすこと |
| 子をもって知る親の恩 | 自分が子供を持ってはじめて、親のありがたみがわかること |
| 虎穴に入らずんば虎子を得ず | 大きな利益や成果を得るためには危険を冒す必要があること |
| 胡蝶の夢 | 人生が夢のようにはかないこと (胡蝶って何の動物でしょうか) 答:蝶 美しく表現したら胡蝶になります |
サ行
サから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 酒は百薬の長 | お酒は適量であれば、どんな薬にも勝るお薬になること。 |
| 匙を投げる | 手の施しようがなくなり、医者が治療をあきらめること 成功する見込みがなくなって、あきらめること (匙ってなんのことですか?) A:カレースプーン B:お薬を調合する匙 C:ティースプーン 答:B |
| 猿も木から落ちる | 優れた人でも、たまには失敗すること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:弘法にも筆の誤り、河童の川流れ |
| 触らぬ神に祟りなし | 余計な口出し手出しはしない方がいいこと 神様に触れなければ祟りが無いように、余計なことに手を出さなければ災いもない |
| 山椒は小粒でもぴりりと辛い | 山椒の実は小さいが、激しい辛さをしていることから、小柄でも気性が激しく、才能にもめぐまれた、決して侮ってはいけないような者のこと |
| 三度目の正直 | 一度目、二度目がうまくいかなくても三度目にもなればうまくいくこと |
| 三人寄れば文殊の知恵 | 普通の人でも三人集まれば、文殊菩薩のように良い知恵が出てくるという意味 |
| 三顧の礼 | 三顧というのは三度訪れるということです。 目上の人が、仕事を引き受けてもらうのに何度も足を運んで礼を尽くすこと。 中国の蜀(しょく)の国の劉備(りゅうび)が諸葛孔明(しょかつこうめい)に軍師になってもらうため三度訪ねたという故事からなっています。 (この物語のタイトルはなんでしょう) 答:三国志 |
シから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 地獄で仏 | ひどく困った状況のときに、思わぬ助けに合うこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:闇夜の提灯(ちょうちん) |
| 地獄の沙汰も金次第 | お金を積めばどんなことも思い通りに出来るという意味 沙汰というのは裁判のこと、地獄での裁判もお金を積めばどうとでもなるので、ましてこの世ならなおさら |
| 獅子身中の虫 | 内部の者でありながら、その内部に災いをもたらすもののこと (獅子って何の動物でしょうか) 答:ライオン |
| 失敗は成功のもと | 失敗しても、原因を見つけ、次は失敗しないように心がけることで、いつか成功への道が開ける |
| 朱に交われば赤くなる | 付き合う人次第で、人は良くも悪くもなること |
| 鎬(しのぎ)を削る | 鎬というのは、刀の刃と峰の間の部分で、鎬が削れるくらい激しく切り合うという意味なので、激しく争うことのたとえ |
| 春眠暁を覚えず | 春の夜は心地よく眠れるので、朝が来たことも気づかず、簡単に起きれないこと |
| 勝負は時の運 | 勝負事は実力で決まるのではなく、運やはずみで決まることもあるということ |
| 食指が動く | 食欲がわいたり、何かあるものが欲しくなったり、何かをしたくなったりすること (食指とは、どの指でしょうか?) 答:人差し指 |
| 白羽の矢が立つ | 大勢いる中から特別に選び出されること 人身御供に選ばれた少女の家に白羽の矢のついた矢を指したことが由来 |
| 知らぬが仏 | 知れば腹の立つようなことでも、知らなければ平気でいられること |
| 親しき仲にも礼儀あり | どんなに親しい間柄でも礼儀が必要 遠慮がなくなると仲が悪くなる原因になる |
スから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 好きこそものの上手なれ | 好きなものは熱心に取り組むので、上達するのも早くなる |
| 過ぎたるは猶(なお)及ばざるが如し | やり過ぎることは、控えめ過ぎるのと同じくらいでよくない ほどほどがよい |
| 杜撰(ずさん) | 誤りなどが多くいい加減なこと |
| 脛(すね)に疵(きず)持つ | 過去に悪事を働いたことを隠してうしろめたいこと |
| 住めば都 | どんなに不便なところでも住んでいく間に愛着もわき、都のように良く感じること。 |
| 捨てる神あれば拾う神あり | 世の中では、人に見捨てられてしまうこともあるが、反対に手助けをしてくれる人もいるので、くよくよしてはいけないという教え。 |
| 雀百まで踊り忘れず | 人は幼い時に見つけた習慣を、歳を取ってもなかなか直すことができないことのたとえ (なかなか直せない習慣やクセとかありますか?) (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:三つ子の魂百まで |
| 水魚の交わり | 水と魚の関係のように切っても切れない友情のこと |
セから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 青天の霹靂(へきれき) | 突然思ってもいない出来事や事件が起こること また、そういった出来事によって受けた衝撃のこと (霹靂って何のことですか?) 答:雷のこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:寝耳に水 |
| 赤貧洗うがごとし | すべて洗い流したかのように何ももっていない貧乏ぶりのこと |
| 背に腹は代えられぬ | もっとも大事とするもののために、小さな犠牲はやむを得ないとすること |
| 船頭多くして船山に上る | 船に船頭が多いと、指示者が多すぎて船が山に登ってしまうという意味から、指揮をとるものが多すぎると、まとまりがつかず思いもよらに方向に事が進んでしまうことがあるということ |
| 善は急げ | 良いと思ったことは、すぐに行いなさいという教え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:思い立ったが吉日 |
| 千里の道も一歩より | どんな大きなものごとも、小さなひとつひとつの積み重ねから始まるということ |
| 前門の虎後門の狼 | ひとつ難を逃れても、すぐにまた別の難におそわれること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:一難去ってまた一難 |
| 栴檀(せんだん)は双葉より芳し | 栴檀というのは白檀(びゃくだん)という香木のことで、白檀は双葉の頃から良い香りが立っているということで、将来大成する人は幼いころから優れているというたとえ |
| 清濁併せ吞む | 善も悪も関係なくすべて受け入れる度量の大きなこと |
ソから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 俎上(そじょう)の魚 | 俎上とはまな板の上という意味 まな板の上の魚のように、されるがままになるより仕方ない状態のこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:まな板の鯉 |
| 糟糠の妻 | 糟はさけかす、糠はぬかの意味。つまり粗末な食べ物を食べていた貧しかった頃から長年連れ添った妻のこと |
| 袖すり合うも他生(たしょう)の縁 | 道で他人と袖がふれ合うような些細な出来事も、前世からの因縁によるものだから、人との出会いを大切にするようにという教え 他生とは、多生とも書きますが、前世のことを指しています |
| 備えあれば憂(うれ)いなし | 普段から万一の場合を考えて準備しておくと、いざという時慌てず対応できること |
| 損して得取れ | 一時的に損をしたとしても、それが元になって先で大きな利益を得ること |
タ行
タから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 対岸の火事 | 向こう岸の火事はこちらの岸に飛び火することがないように、自分にはなんの危険も影響もないこと |
| 大は小を兼ねる | 大きいものは小さいものの代わりになるが、小さいものは大きいものの代わりにならないので、大きいものの方が役に立つ |
| 高みの見物 | 高い所から見渡すように、自分に害の及ばないところから興味本位でみること |
| 他山の石 | 他人の悪い言動や、行いを見て、戒めとすること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:人のふり見て我がふり直せ |
| 脱兎の如し | 逃げるウサギのように行動がすばやいこと |
| 立て板に水 | 立てた板に水を流した時のように、弁舌がよどみなくすらすら話すこと |
| 蓼(たで)食う虫も好き好き | 蓼というのは葉の辛い植物で、これを好んで食べる虫がいるように、好みは人それぞれということ 物好きな人のこと |
| 立てばシャクヤク座れば牡丹、歩く姿はユリの花 | 美しい女性の姿や、ふるまいを美しい花にたとえたもの |
| 棚から牡丹餅(ぼたもち) | 思いもよらない幸運に見舞われること |
| 旅は道連れ世は情け | 旅に出る時は誰かと一緒が心強いように、世の中もお互い助け合っていくのが大切であるという教え |
| 便りの無いのは良い便り | 何も言ってこないのは、それだけ無事にいる証拠である |
| 短気は損気 | 短気を起こしても、何の得もなく、むしろ自分が損をする |
| 断腸の思い | 腸が断ち切られんばかりの辛い思いのこと |
チから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 長所は短所 | 長所も考えようによっては短所であること |
| 塵も積もれば山となる | 塵のようにわずかなものでも、たくさん集まれば山のように大きなものになるということ (みなさんの「チリツモ」体験を教えてください) |
| 竹馬の友 | 幼いころ一緒に竹馬で遊んだような幼馴染のこと (みなさんにも竹馬の友はいますか?) |
| 治に居て乱を忘れず | 平時でも乱世のときを忘れてはいけない 万一の場合に備えよという意味 |
| 忠言耳に逆らう | 役に立つ忠告ほど、耳が痛いものが多い |
| 血は水よりも濃い | 血のつながりは、他人とのつながりより親密で頼りになる 人の性格などは遺伝によるところが大きいという意味合いにも使われます |
ツから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 月と鼈(すっぽん) | 形が似ていても全く違うもの (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:提灯に釣り鐘 |
| 辻褄(つじつま)を合わす | 話しの前後を合わせて筋が通るようにすること |
| 爪に火を点す | とても貧しいこと または倹約すること、ケチなこと |
| 爪の垢を煎じて飲む | 優れた人にあやかろうとすること |
| 面の皮が厚い | 恥知らずで厚かましい、図々しいこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:厚顔無恥 |
| 鶴の一声 | 議論がまとまらないときに、権威、実力などのある人が一言ですべて決定すること |
| 鶴は千年、亀は万年 | 長寿でおめでたいこと |
テから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 敵に塩を送る | たとえライバルであっても、相手が困っているときは助け船を出すこと。 (このことわざの由来が分かる人はいますか?) 答:戦国時代、武田信玄が塩が手に入らずに困っていたところ、ライバルの上杉謙信が塩を送って助けたという逸話 |
| 手塩にかける | 自分の手で大切に育てること |
| 鉄は熱いうちに打て | 人は柔軟で純粋な若い時に、心身ともに鍛えておくべきであること 何事も情熱の熱い時み実行せよという教え |
| 出物腫れ物所嫌わず | おならやできものは、時と場所にかかわらず出てくること |
| 出る杭は打たれる | 才能のある人は目立ってしまい、周りの人からねたまれたり、憎まれたりすること。でしゃばって周りから責められたりすること。 |
| 伝家の宝刀 | 先祖代々に伝わる家宝の刀のこと つまり、いざというときだけ使う奥の手、切り札 |
| 天災は忘れたころにやってくる | 災害というのは、人が災害のことを忘れて警戒心が薄れた頃にやって来るので、普段から油断してはいけない |
| 天に向かって唾す | 人に危害を与えようとして、自分がその危害を受けること |
| 天高く馬肥ゆ | 空が高く、馬がたくさん草を食べ太る季節 秋の豊さをたたえる表現 |
トから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 豆腐に鎹(かすがい) | 豆腐に鎹を打っても何の反応もないように、手ごたえのないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:ぬかに釘、のれんに腕押し |
| 灯台下暗し | 身近過ぎて、気づかないことのたとえ |
| 遠い親戚より近くの他人 | 遠くに住んでいる親戚の人より、近くに住んでいる他人の方が頼りになること |
| 時は金なり | 時間というものはお金と同じくらい貴重なものであるから、無駄にしてはいけない |
| 毒を以て毒を制す | 悪を制するのに、他の悪を利用すること |
| ところ変われば品変わる | 土地が変わると、同じものでも使い方、呼び方が変わるように、地域によって習慣などが違うこと |
| トビがタカを生む | カエルの子はカエルの逆で、凡人の親から優れた子どもが生まれること |
| 飛ぶ鳥を落とす勢い | ものすごく勢いのある者や勢力のこと 勢いある権力者などに使います |
| 虎の威を借る狐 | 自分はなんの力もないのに、力のある人にくっついて威張ったり好き勝手する人 |
| 団栗(どんぐり)の背比べ | あまり差がないこと 似たり寄ったりで、特に優れたものもいないこと |
| 鳶に油揚げをさらわれる | トンビがサッと降りてきて油揚げをかっさらって行くように、あっという間に大事なものを取られてしまうこと |
| 飛んで火にいる夏の虫 | 夏の虫が火に飛び込んで死ぬように、自分から危険なところに首を突っ込んでいくような愚かな人のこと (ヒント:時代劇でよく使われることわざです) |
ナ行
ナから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| ない袖は振れぬ | お金や物がなくて、どうかしてやろうにも、どうにもできないことのたとえ |
| 長い物には巻かれよ | 権力者など強いものには逆らわないで、言いなりになっておく方が賢明である |
| 流れに掉(さお)さす | 成り行きに合わせて物事をうまく進めること |
| 泣きっ面に蜂 | 泣いているところにさらに蜂が指して、不幸に不幸が重なること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:弱り目に祟り目 |
| 梨のつぶて | 連絡しても応答がまったくないこと 梨と無しをかけている つぶては小石のことで、小石は投げたら返ってこないから |
| 七転び八起き | 何度失敗してもくじけず立ち直ること。 |
| 習わぬ経は読めぬ | 知識や経験のないことは、やれと言われてもできないこと |
| 生兵法(なまびょうほう)は大怪我の基 | いい加減な知識や技術では、大失敗してしまうこと |
| なめくじに塩 | 苦手なものを相手にしては、だらしなく委縮してしまうこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:青菜に塩 |
ニから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 煮え湯を飲まされる | 信頼している者に裏切られてひどい目に合うこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:飼い犬に手を嚙まれる |
| 二階から目薬 | 二階から一階にいる人に目薬を差そうとする行為のように、まわりくどくて効果のないことの例え |
| 逃がした魚は大きい | 一度手に入れかけて、もう少しのところで逃してしまうと、ことさらに素晴らしいものに思えること |
| 逃げるが勝ち | 愚かな争いはしない方がいいという教え その場を離れて相手に勝を譲った方が、結果的に後で利益を得ることがあるということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:三十六計逃げるに如かず、負けるが勝ち |
| 煮ても焼いても食えぬ | どうにも持て余すこと、手に負えないこと |
| 二兎を追う者は一兎をも得ず | 一度に二つのものを得ようとして、結局は一つも得ることができないこと 欲張ってはだめということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:虻蜂(あぶはち)取らず (反対の意味にあたることわざを知っていますか?) 答:一石二鳥、一挙両得 |
| 二の舞 | 前の人と同じ失敗をすること |
ヌから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| ぬかに釘 | 何の手ごたえもないこと、意味のないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:豆腐に鎹(かすがい)、のれんに腕押し |
| 盗人猛々しい | 盗みをしていながら、反省もせず逆に喰ってかかること |
| 濡れ手で粟 | 苦労もなく、たやすく利益を得ること |
ネから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 猫に小判 | どんなに価値あるものでも、それが分からないものには何の役にも立たないこと、反応がないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:豚に真珠、馬の耳に念仏 |
| 猫も杓子も | 誰もかれもみんな |
| 猫の手も借りたい | 非常に忙しい時に、誰でもいいので手伝って欲しいというたとえ |
| 年貢の納め時 | ずっと続けてきたことに見切りをつける時 悪いことを働いていた人が、捕まった時 |
| 猫に木天蓼(またたび) | 大好物のこと (漢字を書いて読みを当ててもらうこともできますね) |
| 猫の首に鈴を付ける | よいアイディアだが、実行に移すのは困難なこと ネズミが猫が近づいたのが分かるように、首に鈴をつけようと考えたものの、誰一人行こうとしなかったという寓話から |
| 念には念を入れよ | 注意の上にさらに注意せよという教え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:石橋を叩いて渡る |
ノから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 残り物に福がある | 人が取りつくして最後に残ってしまったものに、案外良いものがあるということ 人と争わないような人が、思わぬ幸運をつかむこと |
| 喉元過ぎれば熱さを忘れる | 苦しかったことも、その時が過ぎてしまえば忘れるということ また、苦しい時に受けた恩を、楽になったら忘れていること |
| 乗り掛かった舟 | かかわりを持ってしまった事柄を途中で投げ出せなくなること |
| のれんに腕押し | 反応がないこと、張り合いがないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:ぬかに釘、豆腐に鎹(かすがい) |
| 能ある鷹は爪を隠す | 才能がある人は、普段はそれを見せびらかすことはせず、隠していること (実は私も隠してる才能ありますという方いますか?隠れた特技、面白い特技など教えてください) |
ハ行
ハから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 背水の陣 | 決死の覚悟で事に当たること 川や湖を背にして戦をすると、後退すれば水に溺れるので兵士が決死の覚悟で戦うという故事 |
| 馬鹿と鋏は使いよう | 愚かなものでも使いようによっては使える |
| 掃き溜めに鶴 | 環境の良くないところに、不釣り合いなほど美しいものがいたりすること |
| 化けの皮が剝がれる | 本当の姿、素性などが暴かれ、正体が現れること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:馬脚を露す、尻尾を出す |
| 箸にも棒にもかからぬ | どうにも扱いようがないこと |
| 八方ふさがり | どっちを向いても行き詰っている状態 |
| 花より団子 | 風流よりも実益重視なこと 風流が分からない人のこと |
| 歯に衣着せぬ | 遠慮せずはっきりものを言うこと |
| 花に嵐 | よいことには邪魔が入りやすいことのたとえ |
| 花も実もある | 外観、中身ともに充実していること |
| 腹が減っては戦が出来ぬ | 何かを始めるには準備が十分でなくてはならないということのたとえ |
ヒから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| ひいきの引き倒し | ひいきするつもりがやり過ぎて、返って迷惑をかけてしまうこと |
| 人のふり見て我がふり直せ | 人の姿、ふるまいを見て自分の欠点を改めようとすること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:他山の石 |
| 人は見かけによらぬもの | 人の外見だけでは、その人のことを判断できないこと 外見と中身は案外違うもの |
| 火のない所に煙は立たぬ | 火が無い所に煙が立たないように、何の根拠もないのに噂だけが立つことはないということのたとえ |
| 百害あって一利なし | 害ばかりで、利益になることが一つもないこと |
| 瓢箪(ひょうたん)から駒 | 考えられないようなことが起こったり、冗談で言ったことが現実になったりすること |
| 火を見るよりも明らか | 疑いようがないくらい明らかなこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:自明の理、明々白々 |
| 貧乏暇なし | 貧乏で働き続けないといけないので、暇がないこと |
| 百聞は一見に如かず | 人からの話をどんなに聞いても、実際に目で見ることにはかなわないこと |
フから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 風雲急を告げる | 何か大きな事件が起こりそうな雰囲気の時使います |
| 風前の灯(ともしび) | 風が吹くところにあるろうそくの灯のように、今にも滅びそうなもののたとえ |
| 覆水(ふくすい)盆に返らず | 一度こぼれてしまった水は二度と盆に戻らないことから、一度やってしまったことは取り返しがつかない |
| 武士は食わねど高楊枝 | 武士は貧しくてご飯を食べていない時でも、食べたふりをしてゆったりと楊枝を使い、弱みを見せないこと |
| 豚に真珠 | 価値の分からないものに高価なものを与えても意味がない、無駄である (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:猫に小判 |
| 刎頸(ふんけい)の交わり | とても親しく交際すること 刎頸(ふんけい)というのは首をはねられること その友のために首をはねられても惜しくないくらい親しい間柄 |
| 武士は相見互(あいみたが)い | 武士は武士同士、立場が同じなので助け合おうということ 同じ立場同士の者は、お互いに助け合おうという教え |
へから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| へそで茶を沸かす | あまりの馬鹿馬鹿しさに大笑いせずにいられないことのたとえ |
| 下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる | 下手なことでも数多くやっているうちにまぐれが起こる 簡単にあきらめずに何度も挑戦せよという教え |
| 下手の長糸、上手の小糸 | 裁縫が下手な人ほど、糸を長くとって失敗するが、上手な人は必要な長さだけをとって手際よく縫ってしまう 仕事も同じで下手な人は無駄が多く、上手な人は手際が良い |
| 下手の横好き | 下手なのに、その物事を一生懸命好きでやること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:好きこそものの上手なれ |
| 屁を放(ひ)って尻すぼめる | 人前でおならをしてしまってから、慌てて尻をすぼめるように、失敗してから急いでごまかすこと |
| 弁慶の泣き所 | 足のすねのこと その人の弱点のことも指す |
| 下手の考え休むに似たり | 下手な人が時間を考えてもよい考えは浮かばないから、休んでいるのと変わらない 時間の無駄なこと |
ホから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い | あまりにも誰かのことが憎らしいと、その人に関わるあらゆる物まで憎らしく思えること |
| 臍(ほぞ)を噛む | 及ばないこと、後悔してもどうしようもないこと (臍とは何の事でしょう?) 答:へそのこと |
| 仏作って魂入れず | 一番肝心なものが抜けていること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:画竜点睛を欠く |
| 仏の顔も三度 | 仏様のような穏やかな人でも、何度も失礼されれば怒り出すこと |
| 骨折り損のくたびれ儲け | 労力ばかりかかったのに、なんにもならず、無駄にくたびれただけのこと |
| 惚れた欲目 | 好きになってしまった相手のことは、実際以上に良く見えてしまうこと 欠点でさえ良く見えること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:あばたもえくぼ |
マ行
マから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 蒔かぬ種は生えぬ | 原因が無いのに結果は生まれないこと 努力なしに結果を得ようとしても無駄なこと |
| 馬子にも衣裳 | どんな人でも身なりを整えればそれなりに見えること 馬子というのは、馬で人や荷物を運んでいた人で、粗末な身なりをしていたことから |
| 松かさより年かさ | 年を取った人の経験や知恵は役に立つということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:亀の甲より年の功 |
| 待てば海路の日和あり | 今はうまくいってなくても、いつかチャンスが来ることもあるので、あせらず待てという教え (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:果報は寝て待て |
| 眉唾 | 嘘ではないかと疑っていること 眉に唾を付けて見るとだまされないという迷信から |
| 真綿で首をしめる | 時間をかけてじわじわと責めること |
ミから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 木乃伊(みいら)取りが木乃伊になる | 説得しようとした人が、逆に説得されてしまったりすること |
| 身から出た錆(さび) | 自分のしたことの報いで不幸に遭うこと |
| 見ざる聞かざる言わざる | 人の欠点や、自分に都合の悪いことは、見ない、聞かない、言わないようにすること |
| 水清ければ魚棲まず | 水がきれいすぎると隠れる場所がないので魚が住みつかないのと同じで、人間も清廉潔白すぎると人に敬遠されること |
| 三つ子の魂百まで | 幼いころの性格は、大人になっても変わらないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:雀百まで踊り忘れず |
| 実るほど頭が下がる稲穂かな | 稲穂が実ると重さで穂先が下がってくるように、人間も学問や徳が深くなると自然と、謙虚になってくるということ |
ムから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 昔取った杵柄(きねづか) | 昔習得した技などが、衰えていないこと (みなさんの昔取った杵柄は何ですか?) |
| 矛盾 | つじつまが合わないこと 中国の楚(そ)の国で、盾と矛を売る男が、この盾はどんな矛でも防ぐことができる。矛はどんな盾も貫くことができると言い、客にその矛で盾を貫いたらどうなるか聞かれたものの、答えることができなかったという故事が由来です |
| 無用の長物 | 何の役にも立たず、邪魔なもの |
| 無理が通れば道理が引っ込む | たとえ筋が通っていないことでも、一度でも通用してしまえばそれが正しいことになってしまい、元の道理がなくなってしまうこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:勝てば官軍負ければ賊軍 |
メから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 目から鱗が落ちる | 何かのきっかけで、今まで分からなかったものがはっきり分かるようになること |
| 目糞鼻糞を笑う | 自分の欠点は分からずに、人の欠点をけなすこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:五十歩百歩 |
| 目白押し | 多くの人が混みあって並ぶこと、また、物事が集中して続くこと メジロが枝の上に身を寄せ合うように並んでとまることから |
| 目の上の瘤(こぶ) | 自分より目上など立場が上の人に対して、邪魔で目ざわりと感じること |
| 目は口ほどにものをいう | 口で言わなくても、目は同じくらい相手に気持ちを伝えること 言葉には出していない本音などが、目には出ること |
| 名所に見所なし | 名所と呼ばれる場所は、行ってみると案外パッとしないことが多いように、名声というものも実際は大したことがないことが多い (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:名物に旨い物なし |
モから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 餅は餅屋 | どんなことでも専門家に任せた方が、安心で間違いないこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:海のことは猟師に問え |
| 元の木阿弥 | 一旦良くなったのに、また元に戻ること 木阿弥という僧が歳を取って、元妻のところに戻ったことで、積んだ修行がパーになったなど諸説あり |
| 諸刃の剣 | 両面が刃の剣は、相手だけでなく自分自身も傷つけやすいことから、素晴らしい面と危険と両方併せ持つもののたとえ |
| 門前の小僧習わぬ経を読む | 寺の門前に住む子供は、いつも経を耳にするので習ったことがなくても覚えてしまうことから、普段身近に接している者に影響を受けること |
| 物は試し | 何事もやって見なくては分からないので、とりあえずやってみろという教え |
| 桃栗三年柿八年 | 芽が出て実がなるのに桃、栗は三年かかり、柿は八年かかるということ それだけ辛抱強くいなければいけないという教え (この続きが分かる方はいますか) 答:梅は酸(す)いとて十三年、柚(ゆず)は九年の花盛り、びわは九年でなりかねる |
ヤ行
ヤから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 焼け石に水 | 焼けた石に少量の水をかけても蒸発して何にもならないように、わずかばかりの助けでは効果がないこと |
| 焼け木杭に火がつく | 一度消えたように見えた燃えさしが、また燃え出すことがあるように、別れた男女の仲も、ちょっとしたきっかけでまた元に戻りやすいこと |
| 柳に風 | 柳の枝が風に逆らわずたなびくように、相手に上手に合わせること |
| 藪から棒 | 藪から棒が突然出てくるように、予想外のことが突然起きること (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:青天の霹靂(へきれき) |
| 藪をつついて | 余計なことをして災難を招くこと 藪蛇(やぶへび)ともいう |
| 病は気から | 病気は案外気の持ちようからということ |
| 闇夜に提灯 | 真っ暗闇の中で提灯が頼りになるように、心細いとき頼れるものに会うこと (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:渡りに船、地獄に仏 |
ユから始まることわざ
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 有終の美を飾る | 物事を成し遂げ、立派な結果を残すこと |
| 湯を沸かして水にする | 湯を沸かしたのに、使わずに水み戻ってしまったように、せっかくの苦労が水の泡になること |
| 幽霊の正体見たり枯れ尾花 | 尾花というのはすすきのこと 怖いと思って物事を見ると、なんでもないものも怖いものに見えること |
| 夢は逆夢 | 夢でみたことは現実世界では逆になるので、悪夢を見ても落ち込まないようにという教え |
| 雪は豊年のしるし | 雪の多い年は豊作になるといわれる |
ヨから始まることわざ

| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 葦の髄(ずい)から天井を見る | 葦の髄というのは葦の茎の細い穴のこと そんな細い穴から天井を見ても全部は見えないように、狭い知識などで、大きな物事を決めつけてはいけないという教え |
| 寄らば大樹の陰 | 頼りにするなら大樹のように大きな力を持った者を当てにした方が安心ということ |
| 弱り目に祟り目 | 弱っているときに、さらに災難に見舞われること |
| 世の中は九分(くぶ)が十分(じゅうぶ) | 世の中はうまく行かないものだから、九分うまく行けばそれで十分とすること |
| 夜目、遠目、笠の内 | 女性は夜見る時、遠くから見る時、笠からちら見えする時が実際より美しく見える |
ラ行・ワ行
| ことわざ | 意味 |
|---|---|
| 来年の事を言えば鬼が笑う | 来年のような先の事はどうなるか分からない 先のことをあれこれ考えてみてもわからないということのたとえ |
| 楽あれば苦あり、苦あれば楽あり | 楽しみの後には苦労があり、苦労の後には楽しみがある 苦しくても頑張っていればいつか楽しいこともある (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:楽は苦の種、苦は楽の種 |
| 李下に冠を正さず | 桃の木の下で冠を直すと泥棒に見えることから、紛らわしい行いはしてはいけないという戒め |
| 両手に花 | 一人の男性の両脇に二人の女性がいること |
| 良薬は口に苦し | 良く効く薬ほど、苦いように、人からの忠告なども耳に痛いほど為になるということ (同じ意味の他のことわざを知っていますか?) 答:忠言耳に逆らう |
| 類は友を呼ぶ | 性格や気の合う者同士は自然と集まって仲間を作ること |
| 礼も過ぎれば無礼になる | 度を過ぎた礼儀は、かえって相手にとって失礼になる |
| 六十の手習い | 年を取ってから習い事や稽古事を始めること (60歳を過ぎてから始めたことはありますか?) |
| 論より証拠 | どれだけ議論を重ねても、実物や証拠を見せた方が説得力があること |
| 若い時の苦労は買ってでもせよ | 若い時の苦労は自分を成長させ、将来もその経験が役に立つので、自ら求めてでもするべきである |
| 渡りに船 | 何かしようとするときに、都合のよいことが起きること |
| 笑う門には福来る | 家族の笑いが絶えないような家には、自然と幸せが訪れる |
| 和を以て貴(たっと)しとなす | 聖徳太子の十七条憲法の一文で、人の和を大切にすることがこの世の中では重要である |
まとめ
ことわざを使ったクイズは、高齢者施設でのホワイトボードレクにぴったりです。
ホワイトボードとペンがあればすぐに出来るので、職員の準備も楽ですよね。
ことわざは、日常の会話でも使うので馴染み深いものですが、最初に、「今日は、数字の入ったことわざクイズをします」といった具合に、あらかじめヒントを出しておくと、正答率が上がると思います。
また、表中に太字で書いてあるのは、ヒントやレクを盛り上げるための会話のきっかけです。
利用者さんにも話す機会を持ってもらって、コミュニケーションを楽しんでください。