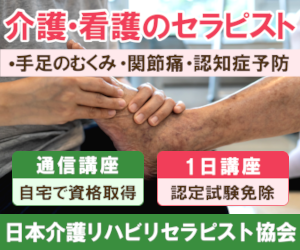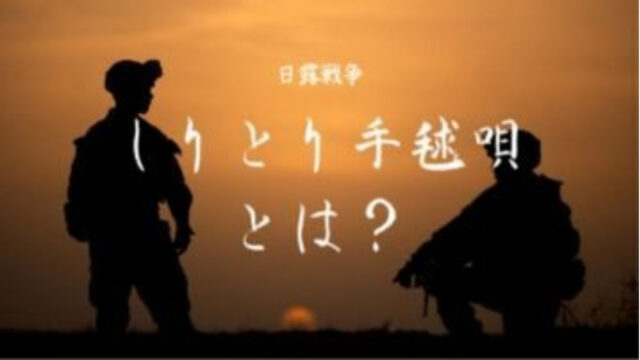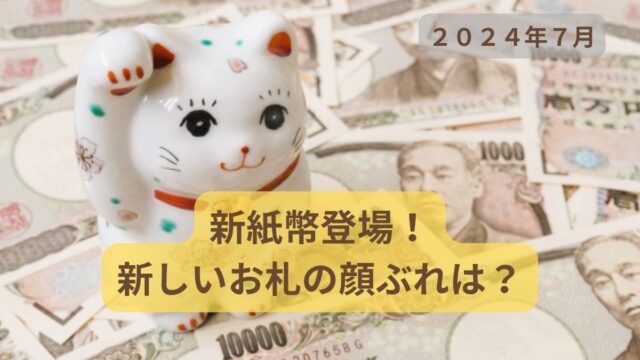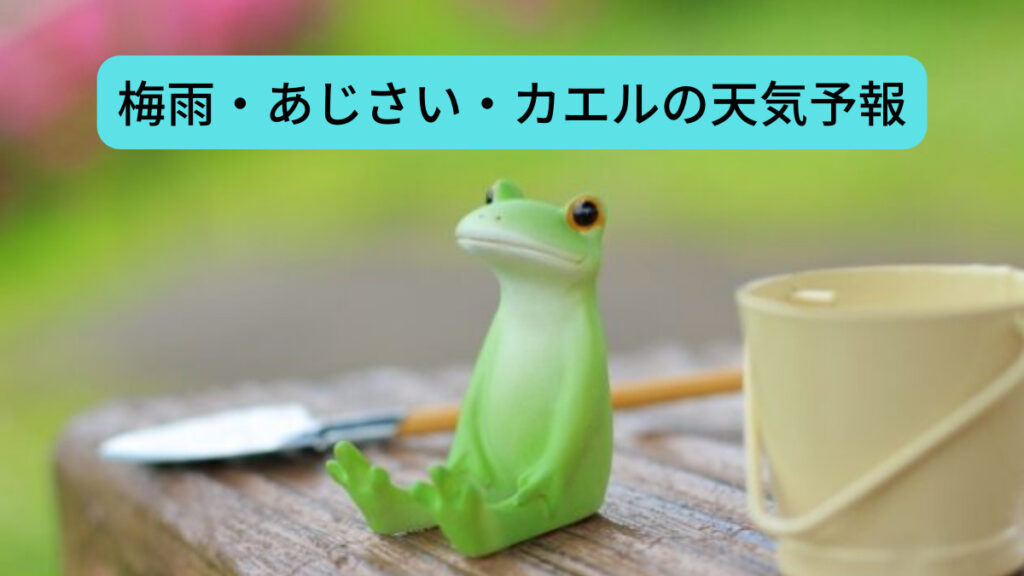
梅雨という言葉を聞くと、どんなイメージが湧きますか?
じめじめ、カビ、鬱陶しい・・
あまりいいイメージではないかもしれませんが、毎年40~50日間はこの梅雨とお付き合いをしなくてはいけません。
ということで、お話のネタとして梅雨のこと、アジサイの花、カエルちゃんの話などいかがでしょうか?
梅雨にまつわる雑学
なぜ梅雨があるのか?
梅雨の時期、日本列島の上空では北からのオホーツク海気団と南からの小笠原気団が押し合いへし合いしています。
このせめぎ合いの最前線に作られるのが梅雨前線で、2つの気団が含む湿気が雨となって降り注ぐわけです。
やがて南の小笠原気団がオホーツク海気団を押し上げて日本の上に勢力を広げると、晴れて梅雨明け夏の到来ということになります。
なぜ梅に雨と書いて「つゆ」と読むのか
ちょうど梅の実がなる頃ですよね。
●梅の実が熟す頃なので、その時期に降る雨として「梅の雨」
●カビが生えやすい時期で、カビ「黴」という漢字は「バイ」とも読みますので「黴雨(バイウ)」。しかし字面が良くないので「梅」の字を当てた。
などの説があります。
「つゆ」と読ませるのは、
●「露」を連想するから
●梅の実が熟して潰れる「潰ゆ(ついゆ)」
など、これまた諸説ありです。
梅雨にまつわる言葉

●梅雨入り、入梅
「入梅」というのは「雑節(ざっせつ)※」のひとつです。
昔は天気予報がないので梅雨の始まりと期間が決められていました。
それによると6月11日頃が梅雨の始まりの「入梅」となり、それから30日後に梅雨明けとなります。
しかしこれをそのまま長細い日本列島に当てはめると、実際と合いません。
なので、実際に梅雨入りした時には「梅雨入り」という言葉を使っています。
※雑節というのは、二十四節気とは別に季節の変化をとらえるための日本独自の暦です。
八十八夜なども雑節です。
●男梅雨、女梅雨
梅雨もその年によって雨の降り方が違います。
男梅雨は、晴天が多いながらも降る時は激しい雨が降るような梅雨のこと。
女梅雨は逆に、しとしとと弱い雨が降る梅雨のことです。
●戻り梅雨、返り梅雨
どちらも同じ意味ですが、梅雨明けの後、再度梅雨が戻ったように雨が続くことをいいます。2022年の夏がまさにそれで梅雨明け宣言が出された後に、また梅雨に逆戻りしたように雨が降りました。
【Q】この頃になるとイワシに脂がのっておいしくなります。
この時期のイワシを何イワシといいますか?
A 脂イワシ
B 入梅(梅雨)イワシ
C 雨イワシ
【答】B 入梅(梅雨)イワシ
アジサイ

梅雨の雨はうっとうしいけど、アジサイの花は好きという方はいらっしゃるのではないでしょうか?
雨に濡れた様子は美しいですね。こんなに雨が似合う花はないですね。
なぜ「紫陽花」と書くのか
まず「アジサイ」という名前については、2つの単語をくっ付けて出来ています。
「アジ」は「集まる」という意味の「あつ」、「サイ」は「藍色」を意味する「真藍(さあい)」という単語です。
つまり「あつ」+「真藍(さあい)」=「アジサイ」となります。
意味としては「藍色の集まり」ですね。
元々日本でアジサイといえば、下の写真の「額アジサイ」のことを指しますので、まさに「小さな藍色の花の集まり」と言うことができそうです。
では、漢字の「紫陽花」はどうでしょう?
これは中国の唐の時代の詩人が全く別の花に「紫陽花」と名付けたのを、日本の学者が「アジサイ」のことと勘違いしてこの漢字を当ててしまったからだと言われています。

これが額アジサイ。日本でアジサイといえば、この額アジサイのことを指していました。
周りの花びらは実は「額」で真ん中の小さいつぶつぶしているのが花。
西洋アジサイ

今はこちらの「西洋アジサイ」の方がよく見かける気がします。
この丸っこい形のアジサイは「西洋アジサイ」といいます。
額アジサイよりよく見かけるけど、名前はいかにも外国から来ましたって感じです。
実は、もともとは日本固有の植物なのです。
それがなぜ西洋アジサイというのかというと、長崎の出島に医師として住んでいたシーボルトが海外に紹介し、海外で品種改良を重ね日本に逆輸入されたから。
ちなみにシーボルトは海外にアジサイを紹介する際、奥さんの滝さんの名前からとって「オタクサ」と紹介しています。
アジサイの色は大きく分けて赤系、青系がありますが、土壌が酸性かアルカリ性かによって色が決まります。では酸性の時は何色になりますか?
A 赤
B 紫
C 青
【答】C 青
土壌が酸性だと青、アルカリ性なら赤、中間は紫です。
日本は弱酸性の土壌が多く、青系や紫系が多いですが、ヨーロッパはアルカリ性の土壌が多く赤系が多いそうです。
6月の6のつく日にアジサイを逆さまにして吊るしておくと魔除けになるそう。
吊るす場所によって
玄関 → お金が貯まる
部屋 → お金に困らない
トイレ → 婦人科の病気にかからない
など。
一年間吊るして、一年経ったら川や海に流すとよいそうです。
カエルが鳴くと雨が降る?
梅雨と言えば「アマガエル」です。
なんせアマガエルが鳴くと雨が降ると言われるくらいです。
カエルはなぜ鳴くのか
カエルが鳴くのはなぜなのか?3つの種類があることが分かりました。
●メスへの求愛
「メイティングコール」と言われ繁殖期にメスにアピールするため鳴きます。
●合唱
●雨鳴き
雨を察知して鳴くといわれる雨鳴き。昼間でも鳴きます。
カエルは雨がわかるのか?
アマガエルが雨の前に鳴くことを「雨鳴き」というそうです。
アマガエルは皮膚が薄いので、気圧や湿度の変化に気づきやすく雨が分かるのではと思われます。
ただ、雨が分かったとして、なぜ鳴くのか理由は分かっていません。
一説では、カエルは全呼吸の3~5割を皮膚呼吸でまかなっていて、雨の前に湿度が上がると活動的になって鳴くのではないかといわれています。
カエルの天気予報は当たるのか?
カエルの天気予報の当たる確率はどれくらいなのかを調べた人がいるようで、それによるとだいたい50~70%くらいの確立で当たるようです。
一方で40%にも満たないというものもあり、実際のところどうなのかははっきりとしませんでした。
ただ、三重県鳥羽水族館では毎年6月1日~8月31日まで「カエルとイモリの天気予報」という取り組みをしています。
ここでのカエルの雨鳴きの成績は、40%台くらいのようです。
しかもカエルよりイモリの方が成績がよいらしく、カエルは下駄以上イモリ以下という落ちがついています。
→鳥羽水族館「カエルとイモリの天気予報」
まとめ
梅雨にまつわる話として、
●梅雨がなぜ梅の雨と書いて、つゆと読ませるのか
●梅雨の様子を表すことば
●アジサイの名前の由来
●額アジサイと西洋アジサイがあること
●カエルの雨鳴きについて
など書いてきました。
じめじめと憂鬱な梅雨ですが、あじさいを眺めたりカエルの鳴き声に耳を傾けたり、意外と梅雨は梅雨で楽しく過ごすことが出来そうですね。