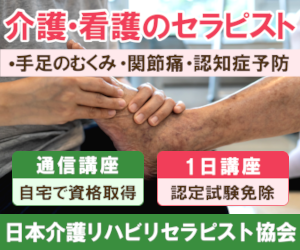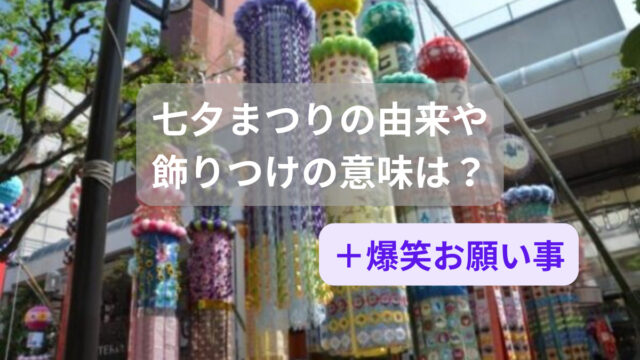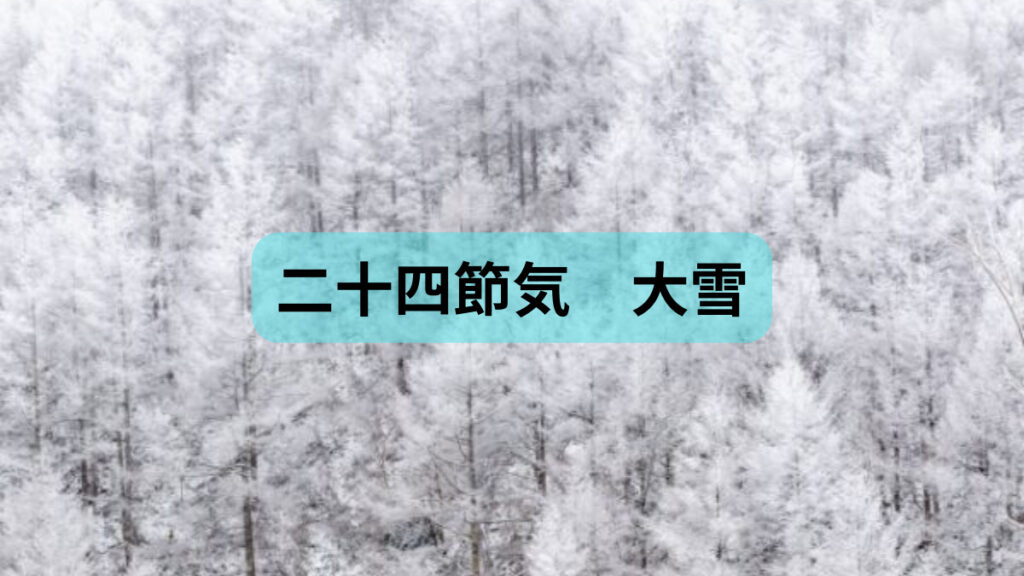
大雪
12月7~21日頃。
いよいよ冬も本番となります。
江戸時代に書かれた「暦便覧」には「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」とあり、雪が激しく降り始める頃のように書いてあります。
が、日本列島は長いので、西日本の方では霜が降りるくらいかな。
北海道では、解ける前に雪が降り積もって積雪状態が続く「根雪」が見られる頃かな。
「雪は豊年の瑞(しるし)」という言葉もあり、昔の人は雪が多いと豊作になると考えていたようです。
七十二候
二十四節気大雪の候は以下の3つです。
初候: 閉塞く冬と成る(そらさむくふゆとなる)

12月7~11日頃。
灰色の重く広がった空、いわゆる「鈍色(にびいろ)の空」をイメージさせますね。
「そらさむく」って「閉塞」と書いてますから、閉じてふさぐことです。
太陽光を通さないってことでしょうか、いずれにしても雲が厚く垂れこめる感じがします。
次候: 熊穴に蟄る(くまあなにこもる)

12月12~16日頃。
そのままの意味です。
熊がそろそろ冬眠に入る頃です。
冬眠といっても爆睡してるわけではなく、物音で目が覚めるくらいの浅い眠りのようです。
木の実など食べこんで栄養を蓄え、寝て冬をやり過ごす。
どんなに寒くても出勤せねばならない人間を思うと、少し熊がうらやましくもあり・・・
末候: 鱖魚群がる(さけむらがる)

12月17~21日頃。
鮭は川で孵化して海へ下り、そこで数年過ごした後、産卵のため生まれ故郷の川に戻って来るという習性があります。
生まれた川を覚えていて戻って来るとは不思議ですね。
「鱖魚(さけ)群がる」とは、鮭が産卵のために群れをなして川を上って来ることをいっています。
北海道のアイヌの人々は、こうして戻って来る鮭のことを「カムイチェプ」(神の魚という意味)と呼んで神様の恵みととらえていたようです。
アイヌの人に限らず東北地方などでも「鮭祭り」をして、豊漁を祈願したりしています。
また鮭にまつわる民話なども多く伝わっています。
例えば鮭と結婚する「鮭女房」、鮭の妖怪が人の命を奪う「鮭のオオスケ」などです。