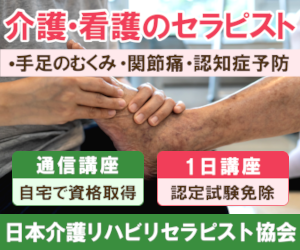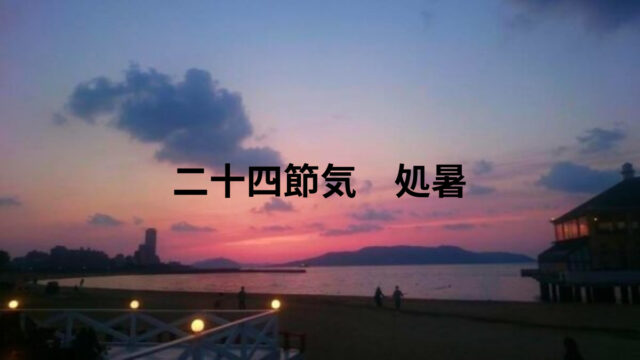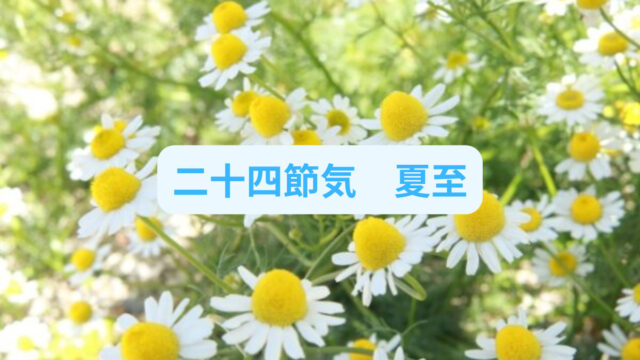スポンサーリンク

スポンサーリンク
秋分
9月23~10月7日頃。
「秋分の日」は「春分の日」同様、太陽が真東から昇り、真西へ沈みます。
また昼と夜の長さもほぼ同じです。
ただ秋分の日以降は、少しずつ日の入りが早くなります。
「秋分の日」については ↓ ↓ ↓

国民の祝日デイサービスなど高齢者施設でのレクに使えるお話のネタをご紹介しています。
国民の祝日について、年間で何日くらいあると思いますか?また、どんな日があるのか、制定の由来や意味は?
さらに祝日と祭日の違いって何?など祝日のことを書いています。
祝日にレク担当になった職員さん、お話しのネタに使ってください。
...
【秋のお彼岸】
秋分の日は秋のお彼岸で、お墓参りをしたり、各地のお寺では法要が行われたりしています。
お彼岸については ↓ ↓ ↓
おはぎとぼたもちの違いや、彼岸花の秘密についても書いています。
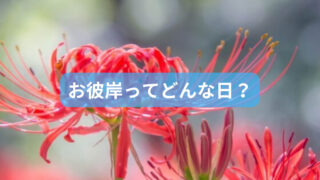
お彼岸ってどんな日?高齢者施設でのレクで使えるお話のネタです。
春と秋の年二回のお彼岸っていったいどんな日なのでしょう?またおはぎと牡丹餅の違いって何?
彼岸花の驚くべき戦略とは?
知ってるようで知らないお彼岸について書いています。...
七十二候
二十四節気秋分の候は以下の3つです。
初候: 雷乃声を収む(かみなりすなわちこえをおさむ)

9月23~27日頃。
春雷に始まって、夏場は夕立でゴロゴロゴロゴロと騒いでいた雷様とも一旦さよならです。
この頃になると雷が聞かれなくなってきます。
そういえば、夏の入道雲もどこへやら、いつの間にか空が高くなって秋の空になってますね。
次候: 蟄虫戸を坯す(すごもりのむしとをとざす)

9月28~10月2日頃。
「蟄虫(すごもりのむし)」とは冬の間を地中で過ごす生き物のこと。
それら蟄虫たちが巣の戸を閉め、冬越しに入ろうとする頃です。
虫たちの越冬の姿はそれぞれです。
・カマキリは卵の状態で草などの茎にくっついて
・コオロギは卵の状態で土の中で
・アゲハ蝶はさなぎの姿で人目につかないところで
・カブトムシは幼虫の姿で腐葉土などの下に
・テントウムシは成虫の姿のまま葉っぱの裏側、木の幹などで(ただし単独ではなく集団で) などなど。
末候: 水始めて涸る(みずはじめてかる)

10月3~7日頃。
黄金色になった稲が頭を垂れて、いよいよ稲刈りのシーズン到来です。
「水始めて涸る」の「水」は田んぼの水のことです。
「涸る」なので、稲刈りの前に田んぼから水を抜いて乾かすことを言っています。