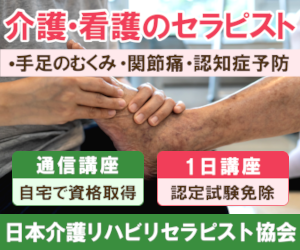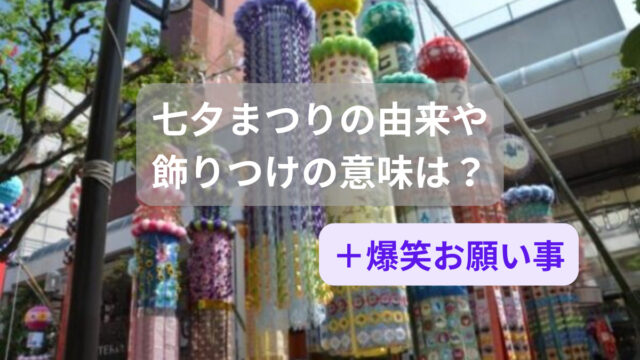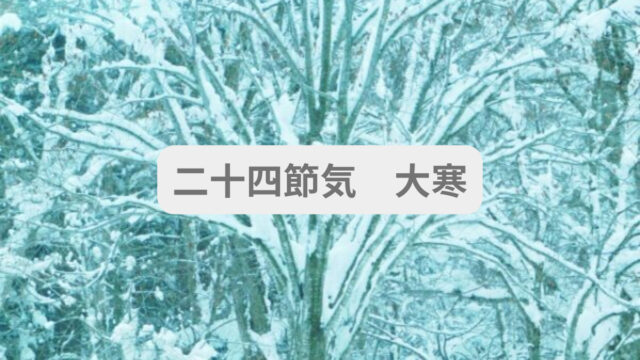春分
3月21~4月4日頃。
「春分の日」は太陽が真東から昇り、真西に沈む昼夜の時間がほぼ等しい日です。
春のお彼岸の中日になります。
気候的にも日脚が伸び、以前より暖かさが増し春本番という感じになります。
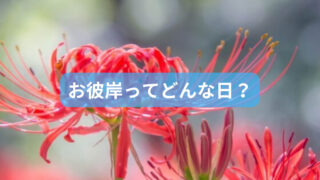
【春季皇霊祭】
春分の日、歴代天皇や皇族方の御霊を祀る「春季皇霊祭」が行われます。
かつては祭日でしたが、1948年(昭和23)より「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として国民の祝日になりました。
七十二候
二十四節気春分の候は以下の3つです。
初候: 雀始めて巣くう(すずめはじめてすくう)

3月21~25日頃。
繁殖期に入る動物が多くなる季節です。
雀も産卵のために巣作りを始めます。
以前は、雀が軒下に巣をつくると家が繫栄するとされていたようです。
次候: 桜始めて開く(さくらはじめてひらく)

3月26~30日頃。
いよいよ待ちに待った桜の花が咲き始める頃です。
末候: 雷乃声を発す(かみなりのこえをはっす)

3月31日~4月4日頃。
冬は雷が少ないですが、春になるとゴロゴロとなり始める、そういう頃という意味です。
【いんげん豆の日】
4月3日。
江戸時代に幕府に招かれて中国(明)からやって来た禅僧「隠元」の亡くなった日。
隠元は、いんげん豆だけでなく、煎茶やレンコン、スイカ、孟宗竹などを伝えたそうです。
食べ物以外でも、京都の黄檗山萬福寺(おうばくざんまんぷくじ)を開き、黄檗宗(おうばくしゅう)を広めました。
またぽくぽくと叩く木魚や、明朝体と言われる書体も、隠元の伝えた経本からだそうです。
【アンパンの日】
4月4日。
1875年(明治8)のこの日、木村屋の初代安兵衛が明治天皇にアンパンを献上しました。
中はこし餡で、真ん中のおへそに桜の塩漬けを埋め込んでいたそうです。
あんこは「つぶあん派」と「こしあん派」に分かれますね。
一般的に関東地方はこしあん派、関西地方はつぶあん派が多いようです。
【歯周病予防デー】
4月4日。
4(歯)周病4(予)防デー。
30~50代の8割が歯周病にかかっていると言われているそうです。
近頃では歯周病が口の中だけの病気ではなく、心臓や肺など前身の病気に関係しているということが言われています。
【大瀬まつり 内浦漁港祭】
4月4日。
静岡県の大瀬神社の例祭で、大漁旗で飾られた漁船の上で、女装の青年により行われる「勇み踊り」が有名。