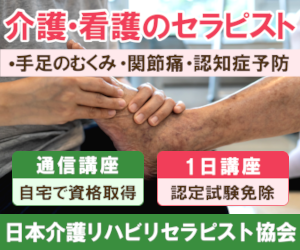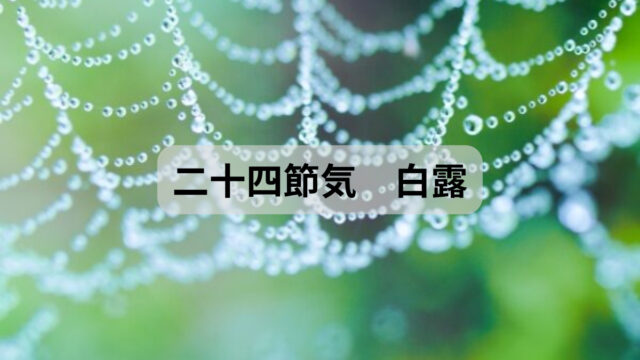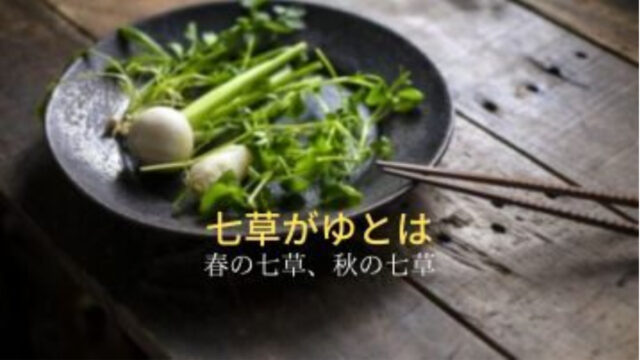スポンサーリンク

スポンサーリンク
小満
5月21~6月5日頃。
「小満」というと字だけではピンと来ません。
なんのこっちゃという感じですが、江戸時代に記された「暦便覧」には「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」とあります。
生き物から植物などありとあらゆる生物すべてが成長し、生命力にあふれた状態のことをいうそうです。
また麦の穂が色づき始める頃でもあり、農家の人が無事に麦が実ったことにひと安心(少し満足)したことから「小満」という説もあります。
七十二候
二十四節気小満の候は以下の3つです。
初候: 蚕起きて桑を食う(かいこおきてくわをくう)

5月21~25日頃。
「起きる」というのは卵からかえること。
蚕が卵からかえり、桑の葉をもりもり食べている様子をあらわしています。
こうして桑の葉を存分に食べた後1カ月ほどして繭をつくり、この繭が絹糸になります。
次候: 紅花栄う(べにばなさかう)

5月26~31日頃。
紅花が満開になる頃を意味しています。
歴史は古く、飛鳥時代に日本に入ってきて、染料や着色料として人々の身近にありました
花びらだけを摘んで使用していたので別名「末摘花」といいます。
末摘花といえば、和歌に多く詠まれていると思う方もいらっしゃると思いますが、ほんとに多いです。
苦しい恋心を紅花の赤い色にたとえたんですね。
「人知れず 思へば苦し 紅(くれない)の 末摘花の 色にいでなむ」 古今集 よみ人知らず
「よそのみに 見つつ恋ひなむ くれなゐの 末摘花の 色に出でずとも」 万葉集 よみ人知らず
末候: 麦秋至(ばくしゅういたる)

6月1~5日頃。
「秋」の字が入っているので、おや?と思ってしまいますが、
「麦秋」、麦の秋
麦が収穫期に入る頃なので、麦にとっての「実りの秋」ということになります。