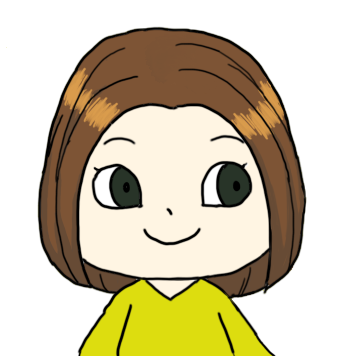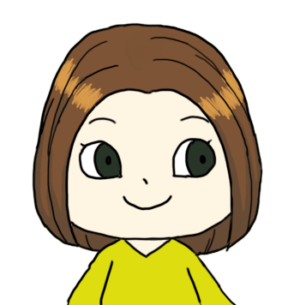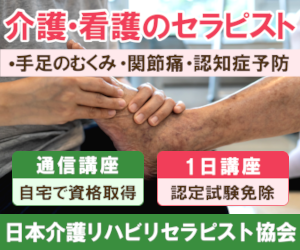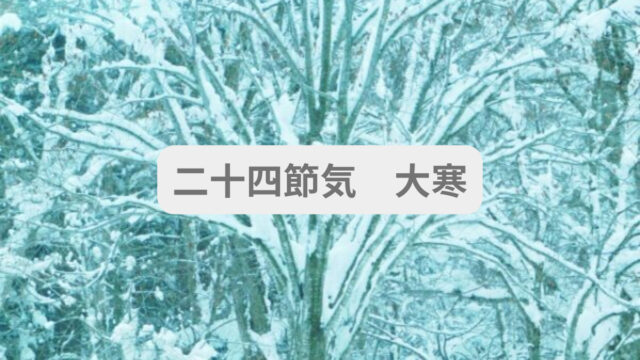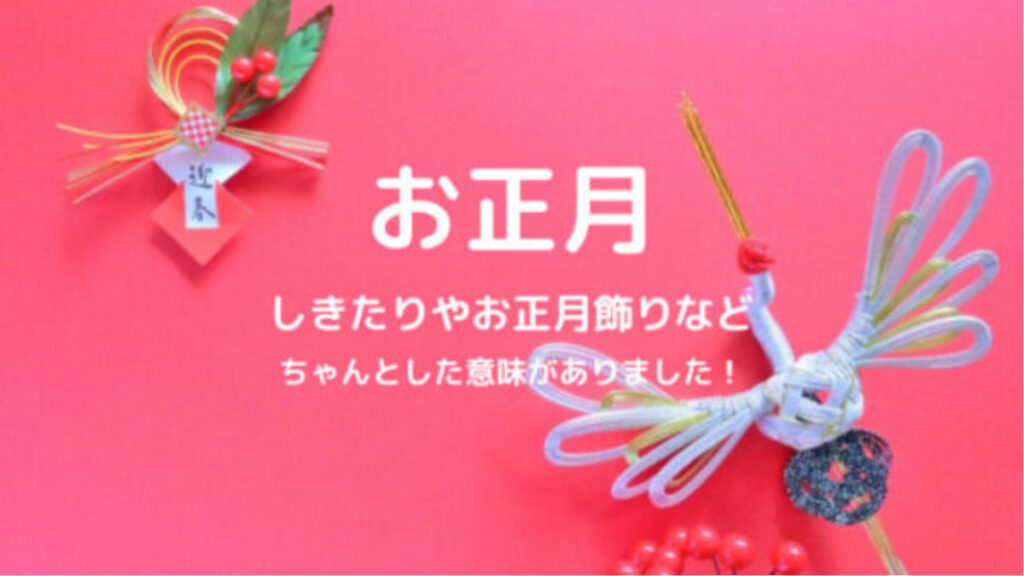
日本人にとって、お正月は一年の始まりの特別な行事です。
年末から大掃除や、年賀状の準備、飾りつけをして、年が明けると初詣、お屠蘇やおせち料理をいただき親戚や友人などが集まって・・・
なんとなくやってますが、それぞれ意味があります。
お正月を迎える準備:12月に入ったら
お正月は年末の準備から始まっているといっても過言ではないですね。
ということでお正月準備にも触れておきたいと思います。
12月13日は正月事始めといい、年神様をお迎えするために、門松の準備やお寺などですす払いを行う日です。
12/15から年賀状の受付が始まります。
今ではメールやラインで済ます人も多いですが、紙の年賀状を出す人もパソコンでちゃっちゃとプリントする人がほとんどでしょう。
元々は親戚や知人等にご挨拶をしてまわった「年始回り」に代わるものとして登場し、明治時代にはがきが発売されると急速に広がり定着したようです。
お正月を迎えるにあたっての買い物をする年の市も始まります。
本来は神社、お寺の境内などで開かれたのですが、デパートなどがある現在では年末セールを年の市と呼んだりしています。
有名なのは17~19日に開かれる浅草羽子板市。
邪気をはね(羽根)返すとして縁起のいい羽子板と羽根のセットが人気です。
その年の話題の人をモチーフにした世相羽子板が有名です。
また各地でイルミネーションが彩をあたえます。
LEDが開発されてからは個人の家を飾り付ける人も多くなりました。
日本三大イルミネーションは、
●ハウステンボス(長崎県)
●あしかがフラワーパーク(栃木県)
●さっぽろホワイトイルミネーション(北海道)
お正月も残り少なくなってくると、歌にもありますがお正月までの残りの日数をなんとなく数えてしまいます。
準備を焦る気持ちと新年を迎える喜びや期待でそわそわしたこの状態を表す言葉がちゃんとあります。
数え日といって、日数を数えることや残りの日数そのものを表していて、季語にもなっています。
お正月の準備:27日~
お正月の飾りつけをいつやるか?これにも色々といわれがあります。
門松、しめ縄、かがみ餅など年内にきちんとしていないと悪いことが起きると信じられていたので、忙しくてもやらない選択肢はなかったようですね。
とはいえ、29日は「二重苦」、31日は「一夜飾り」と言われるので、27日、28日、30日の3日間のどれかでする人が多いです。
お正月飾りは松の内(7日)まで飾ったらその日の夕方までには納め(片付け)ます
納めたら神社のお焚き上げや、地域のどんどやに持っていきます。
28日頃は御用納め、仕事納めが多いですね。
官公庁は御用納め、民間の企業やお店などは仕事納めといいます。
同時にお正月を故郷で過ごすUターンラッシュ、海外で過ごす出国ラッシュも多くなります。
家庭ではおせち作りをする家庭もあると思います。
門松
門や玄関先に左右一対並べます(雄松と雌松)。
年神様が迷わずに訪れることができるよう目印の意味があります。
松は神様の宿る木であると考えられており、さらに縁起の良いとされる竹などを添えるようになったといわれます。
一方で、門松にまつわるお話として、門松の竹が斜めに切ってあるのは、徳川家康が竹を武田信玄の首に見立てて切り落とさせたことが由来だという話もあります。
しめ縄
しめ縄、しめ飾りという呼び方もありますが、漢字で表すと「注連縄」と書きます。
しめ縄を飾っているところは神様をお迎えするにふさわしい神聖な場所であることを示しています。
同時に災いをもたらす不浄なものが入ってこないようにするという意味もあります。
鏡餅

鏡餅ってなんであんな姿なの?
年神様へのお供え物で、床の間や神前にお供えします。
なぜお餅を飾るのかというと、その丸い形を鏡に見立てているからです。
鏡といえば三種の神器のひとつで、鏡をご神体にする神社が多くあるように、餅を鏡に見立て年神様が依り代にされるようにお供えしています。
鏡餅はなぜ2段重ねなのか?
それは大小2段の餅が、太陽と月、陰と陽を表しているとも言われ、また円満に歳を重ねるという願いが込められているとも言われます。
うらじろは何の意味があるのか?
うらじろの葉は裏側が白く、つまり後ろ暗いところがない、清廉潔白を表しています。
また葉の模様が対になっていることから、夫婦仲良く白髪までという願いが込められているそうです。
ゆずりはは新しい芽が出てから古い葉が落ちるので、家を子孫に譲り家系が続いていくことを指しています。
昆布は「よろこぶ」につながる縁起物。
「子生」とも書くので子宝に恵まれるという意味もあります。
橙はそのまま「代々」につながり、家族繁栄を祈ります。
串柿というのは干し柿を串に刺したもので、その見た目から三種の神器の剣に見立てます。
柿は「嘉来」とも書けますので縁起が良いとされています。
鏡餅の餅が「鏡」、橙が「玉」、串柿が「剣」で三種の神器を表しています。
鏡開きとは?
これは年が明けてからのことですが、鏡餅ついでに鏡開きのことも書いておきます。
鏡開きとは、ひとことで言うと鏡餅を食べることです。
1月11日が鏡開きの日とされています。
鏡餅は年神様がいらっしゃった所、つまりパワースポットなので、一年の無病息災を願っていただきます。
食べるという行為が大事なので食べ方は問いません。
焼いて砂糖醤油をつけて海苔で巻いてもよし、きなこもちでもよし、ぜんざいにいれてもよしです。
「開く」という言葉を使うのは、もとが武家の行事であったため「切る」という言葉は切腹をイメージするのでアウト。
実際は木槌(きづち)で割ったりするのですが、「割る」という言葉も縁起が悪いと考えられて使えない、そこで、末広がりという縁起のいい言葉を使って「開く」と表現しました。
「開く」という表現といえば樽開きもそうですね。
樽酒のふたのことを酒屋さんは鏡と呼ぶそうです。
樽酒を開けるときというのは、門出や何か新しいことを始めるときなどですね。
それで、縁起の良い「開く」という表現を使ったようです。
大晦日
大晦日という言葉は、もともと旧暦では毎月最後の日を「晦日」というそうで、一年の最後の日で「大」をつけて大晦日というそうです。
「晦日」には「みそか」の他、「つごもり」という読み方もあるので、大晦日を「おおつごもり」と言ったりもします。
別名では「除日」、古い年を煩悩や罪と共に取り除く意味が込められており、そのためその夜を「除夜」というのですね。
31日大晦日の晩は、お正月の神様である年神様にごちそうをお供えし、「年とり膳」、「年越し膳」といわれるごちそうを家族で食べます。
日本では元来ごちそうといえば魚のこと。
年とり魚と呼ばれ、東日本は鮭(栄える)、西日本は出世魚のぶりを食べます。
年越し蕎麦は江戸時代中期に始まった風習で、蕎麦は切れやすいので悪縁を切る、苦労を切るにつながり、また、細く長いので長寿や家運長久などの願いが込められています。
また、午前12時を過ぎて食べると縁起が悪いと言われています。
大晦日と言えば紅白歌合戦も定番です。
第一回目は1951年(昭和26)年ラジオ放送でした。
テレビ放送になったのは1953年(昭和28)からです。
大晦日の夜は各地の寺院では除夜の鐘が鳴り響きます。
大晦日に全国各地の寺院で108回の鐘をならします。
108回という回数には諸説あります。
・人間の煩悩(人の苦しみのもととなる貪欲などの心の動き)の数
・十二月、二十四節気、七十二候を足したもの
12+24+72=108
・人間が生きていくうえで出会う苦しみである四苦八苦をそれぞれかけて足したもの
四苦(4×9=36)+八苦(8×9=72)=108
などです。
神社では一年の穢れを形代に移し身を清める「年越しの祓(はらえ)」が行われます。
初詣
旧暦では一日は日没から始まるとされ、したがって、新年も大晦日の日没から始まると考えられていました。
なので、年神様は大晦日の夜に来られるということで、一晩中起きてお迎えしたそうです。
その名残から大晦日に早く寝ると白髪になるとか、シワが増えるとかいう言い伝えもあるそうです。
また、旧年のうちに神社を訪れ年越しをするのを初詣とするのは、一家の長が神社にこもり氏神様をお迎えする「年(とし)ごもり」という風習が元になっているそうです。
初詣は、新しい一年が良い年になるよう祈願しに行きますが、本来はその家の氏神様や、その年の恵方(縁起の良い方向)にある神社に参拝していたようです。
決まりはありませんので、自分のお願いごとにあった神社に行くことも多いです。
初詣は松の内(7日)までにお参りします。
そのときは何かひとつ新しいものを身に付けていくと縁起が良いと言われています。
【Q】神社にお参りするときの柏手(かしわで)の打ち方は?
A 一礼二拍手三礼
B 二礼二拍手一礼
C 二礼二拍手二礼
【答】B 二礼二拍手一礼
おみくじ
初詣で今年の運試しにおみくじを引くという方も多くいると思います。
引いたおみくじをどうしていますか?
神社の木にはたくさん結び付けてありますね。
これは木に結びつけても持ち帰ってもどっちでもよいそうです。
多くの人は、大吉などよいおみくじはお守り代わりに持って帰り、凶など悪いときは木に結びつける人が多いようです。
元日
年神様が1年の幸福をもたらすために、降臨する日。
「正月様」「歳徳神(としとくじん)」という呼び方もあります。
「元」という字は「はじめ」という読みもあり、まさに1年のはじめ。
ところで「元日」と「元旦」は別物です。
「元日」は一月一日のことですが、「元旦」の「旦」の字は地平線から昇る太陽を表すので、「元旦」とは元日の朝のことをいいます。
では元日のことをひとつひとつ見ていきたいと思います。
お屠蘇
無病息災、延命長寿を祈って飲む祝い酒です。
屠蘇酒というのは中国から伝わった薬酒で、さまざまな漢方が入っているそうです。
清酒を入れてる家庭もあります。
(熊本は赤酒という熊本でしか作られていないお酒を使います)
お屠蘇を飲む順番は、年の若い順からというのが正式なようです。
なぜなら若い人のパワーを年長者が飲みとるためです。
怖いですね。
また、厄年以外の人が飲んだ杯には厄払いの力があると考えられていて、厄年の人が最後に飲むこともあります。
おせち料理
季節の節目に神様にお供えする「節供(せちく)」がおせちと呼ばれるようになり、お正月の「節供」だけ残ったようです。
よろこびが重なるよう重箱に詰めます。
おせちも一品一品に意味が込められています。
数の子
数の子はニシンの卵ですね。
数が多いので子孫繁栄の願が込められています。
黒豆
まめ(勤勉)に働き、まめ(健康)に暮らせるようにという願い。
黒は魔除けの意味もあり、無病息災を願いました。
田づくり
昔はコイワシが畑の肥料だったので「五万米(ごまめ)」とも書きます。
豊作祈願の意味です。
エビ
長いヒゲ、曲がった腰から老人を思い起こさせますので、長寿を願っています。
きんとん
漢字では「金団」、金の布団に見立てて商売繁盛、裕福な暮らしを願っています。
色も黄金色なので富をイメージさせますね。
昆布巻き
「よろこぶ」に通じる縁起物。
よろこびの席のレギュラーメンバーともいえる存在です。
古代では「ひろめ」と呼ばれており、喜びや名前を広めるという意味もあるようです。
紅白なます、紅白かまぼこ
紅白の水引をかたどったもので、人参の赤が「めでたさ」を、大根の白は「清浄」を表します。
伊達巻
巻物を表しており、学問や文化の発展を祈ります。
たたきごぼう
ゴボウは地中に根を張るので、家の安定や根気よくという意味が込められています。
レクでは、おせち料理の一品一品に込められた意味をクイズのようにすると楽しめると思います
他にも地方や家庭ごとにオリジナルな一品もあるかもしれません
そういった話でも盛り上がると思います
雑煮
年神様にお供えした餅のお下がりを食べたのがその始まりとされています。
お雑煮は地方によって出汁や具材に特徴がありますね。
同じ県の中でも地域により違いがあったりします。
例えば
●香川県
白みその汁にあんこ餅が入っています。
●愛知県
嫁入りの派手なイメージと違い、すまし汁に餅と餅菜(尾張周辺で栽培される小松菜に似た葉っぱ)を入れたシンプルなもの。
●鳥取県
小豆雑煮と呼ばれるぜんざいタイプ。
その他
若水
1月1日の朝、その年初めて汲んだ水のことです。
邪気を払う清らかな水とされているので、年神様にお供えしたり、書き初めの墨をすったりするのに使います。
祝箸
年末に買い物に行くと、お正月用箸として祝箸が売ってあるのを見たことのある方もいると思いますが、その特徴は両端が使えるように細くなっていること。
なぜこうなっているのかというと、一方が年神様、もう一方を私たちが使って年神様と新年を祝うという意味が込められているそうです。
お年玉
お年玉は元々は「年玉」という年神様へのお供え物だったそうです。
中身はお餅やお米だったようです。
その「年玉」を家族や親せきで分けたのが始まりのようで、玉は賜る(目上の者が下の者に贈ること)が変化したとも言われています。
なので、親など目上に贈る時は「お年賀」といいます。
お年玉を入れる袋をポチ袋といいますが、語源は「これっぽっち」から来ているそうです
1月2日 初夢、書き初め
初夢
初夢は一般的には2日の夜に見る夢とされています。
(大晦日、元日の夜、3日の夜など諸説あります)
縁起が良い夢として「一富士二鷹三茄子」は有名ですね。
徳川家康が晩年過ごした駿河(静岡県)の名物で、それが由来という説もあります。
良い夢を見るかどうかで一年の吉凶を占いますので、昔からおまじないがありました。
●七福神を乗せた宝船の絵を枕の下に敷いて寝る
●下の回文を書いた紙を枕の下に敷いて寝る
「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな」
回文とは上から読んでも下から読んでも同じになる文のことです。
室町時代あたりからこの和歌と宝船を書いた絵を枕の下に敷いて寝る風習があったようです。
意味が分かるように漢字を入れると、
「長き夜の 遠の睡りの 皆目醒め 波乗り船の 音のよきかな」となります。
むしろこの回文を枕の下に敷く風習が正式で、のちに簡単にされて七福神の宝船の絵を敷くとなったのではないかと言われています。
書き初め
「初硯(はつすずり)」や「吉書(きっしょ)」とも呼ばれます。
菅原道真を祀る京都の北野天満宮では「天満書(てんまがき)」といって、字の上達を願い書き初めが行われるそうです。
3日 三が日の終わり
いよいよ三が日の終わりとなります。
三が日に雨や雪が降ることを「御降り(おさがり)」と呼んで、豊作のしるしだそうです。
なので、その年のお正月は「富正月(とみしょうがつ)」といい喜ばれたそうです。
松納め
お正月に飾っていたしめ縄や門松を片付けます。
お正月を意味する松の内も今日で終わりとなります。
●飾りつけの意味やおせち料理の具材に込められた願いをクイズにしましょう!
●利用者さんと一緒に鏡餅などの飾りつけをしてお正月の準備をしましょう!