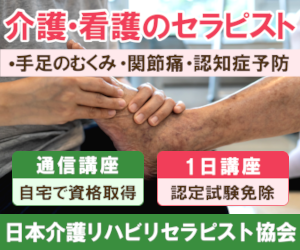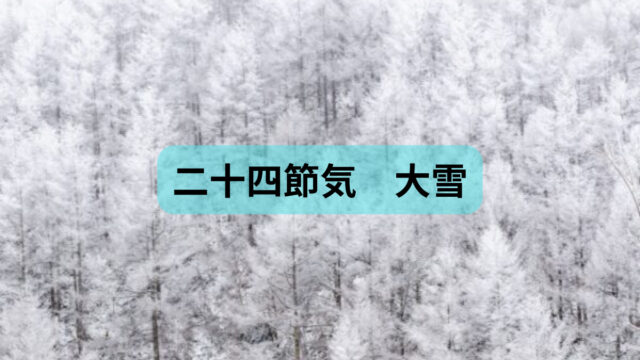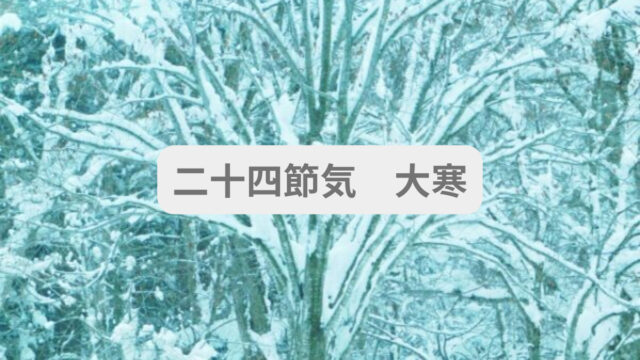スポンサーリンク

スポンサーリンク
立冬
11月8~11月21日頃。
暦の上では今日から冬となります。
しかし、感覚的にはまだまだ秋という感じではないでしょうか?
地域によっては、紅葉もまだこれからという所もあると思います。
二十四節気が中国に由来するので、日本の季節の感覚と少しズレが出るからかもしれませんね。
しかし冬には、また色々な楽しみ方があります。
おでんや、鍋などの食べ物、それを家族や友達と囲む楽しさもあります。
また、子どもにとっては雪遊びや、スケートなどのウインタースポーツも楽しいですね。
イベントもクリスマスや、お正月と楽しいイベントが目白押しです。
七十二候
二十四節気立冬の候は以下の3つです。
初候: 山茶始めて開く(つばきはじめてひらく)

11月8~12日頃。
読みは「つばき」ですが「山茶」と書くと、やはりサザンカですね。
サザンカは秋の終わりから初冬にかけて咲く花です。
似ている花に椿がありますが、椿との大きな違いは花の散り方です。
サザンカは花びらが一枚一枚落ちていきますが、椿は花ごとボトッと落ちます。
なので、椿は首が落ちることをイメージさせ、武家では嫌われていたと言われています。
咲く時期も椿の場合は、早春から春にかけて咲きます。
次候: 地始めて凍る(ちはじめてこおる)

11月13~17日頃。
冷気で霜柱や氷が出来始める頃です。
ここまで来ると、冬が来たなと実感が湧きますね。
夜など冷え込むので、鍋など温かい食べ物が恋しくなります。
末候: 金盞香し(きんせんこうばし)

11月18~21日頃。
「金盞」とは、金の盃という意味です。
金の盃といっても何の事?という感じですが、水仙の花のことだそうです。
水仙の花の真ん中の黄色い部分を金の盃、白い花びらを盃を置く銀の台
にみたてた「金盞銀台」という言葉が中国にあるそうで、それが語源になっているそうです。
また、水仙は寒い冬の中でも咲くことから別名「雪中花(せっちゅうか)」とも呼ばれます。
花の少ない冬の貴重な彩ですね。