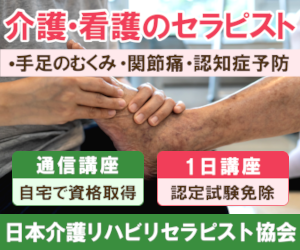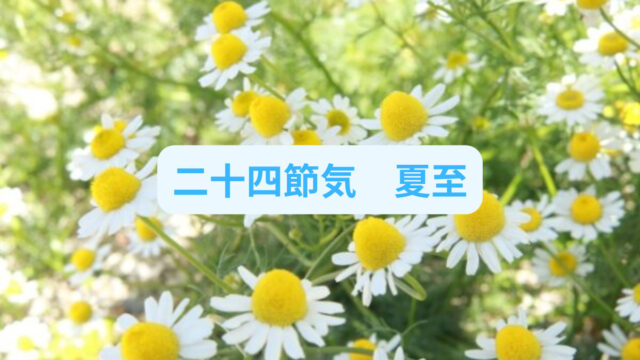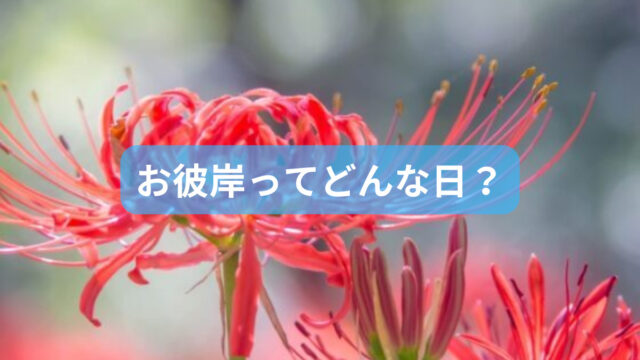節分って何?意味は?
節分は、文字通り季節を分けるという意味で、特に私たちが現在「節分」と呼んでいるのは、「立春」の前日である2月初めの(ほぼ3日になることが多いです)「節分」です。
ほんとうは、季節の分かれ目なので、立夏の前、立秋の前、立冬の前とほかにも3日あるはず。
春だけを特に「節分」として、豆まきなどして特別視するのは、旧暦では春の始まりを新年の始まりとして大切にしてきたからだと言われています。
でも季節の分かれ目って、何がそんなに大事なん?
と思いませんか?
これは、昔から季節の分かれ目には邪気が忍び込むと考えられていたからで、「災い」「病気」などの厄が鬼と結びつけられて、「よし、祓っちゃおう!」っとなったようです。
確かに季節の分かれ目っていうのは、天気や気温に変化も大きく体調を崩しがち。
昔の人が考えて伝えてきた風習には、ちゃんとした理由があるのですね。
鬼を追い払うのに豆をまくのはなぜ?
鬼といわれて思い浮かぶのは、

こんな感じですね。
鬼のように悪いものというのは、今でも鬼門と呼んでいる丑寅(北東)の方角からやって来ると思われていました。
なので、牛のような角を持ち、虎のような牙を持った姿をしているそうです。
では、その鬼を追い払うのに豆をまくのはなんで?
「豆まき」はもともと「追儺(ついな)」と呼ばれ、平安時代から宮中で行われている邪気払いの風習だそうです。
現在でも「追儺式」といって神社やお寺などで行われています。
豆をまくのは、「豆=魔(ま)を滅(め)っする」という意味の語呂合わせです。
豆をまいたあとは食べる
豆をまいて鬼を追い払ったあとは、食べますよね。
豆を食べて福を招き入れます。
自分の年齢と同じ数の豆を食べるのを「年取り豆」といいます。
ところで、豆はどんな豆をまきますか?
本来は炒った大豆をまくそうです。
神棚のあるお宅では、前日から豆をお供えして神様の力を宿しておくそうです。
最近の豆まきでは、衛生面や後片付けを考えると、殻付き落花生とか、5~6粒を一つのパックに詰めたテトラパックをまいたりする家庭も増えているそうです。
炒り大豆は高齢者には固くて食べられませんし、危険です。
●甘納豆などのテトラパックを投げる
●新聞紙を小さく丸めて豆に見立て投げる。
おやつの時にやわらかい豆をいただきましょう。
豆以外にも、恵方巻、いわし、そば
今ではすっかり定着した「恵方巻」もあります。
「恵方巻」というのは、元々は大阪の老舗すし店から始まったといわれています。
その年の恵方(縁起のよい方角)を向いて、切ってない1本の太巻きを食べると病気をしないそうです。
そして最後まで黙って食べなければいけません。
これも高齢者にはちょっと危険。
他には、鬼がきらいなイワシを食べるところもあるようです。
メザシでもよいし、高齢者にはつみれが食べやすいかも。
イワシといえば「やいかがし」といって、イワシの頭をヒイラギの枝に突き刺し、玄関先や門のところに飾る風習もあります。
ヒイラギの尖った枝の先で鬼の目をぶっつぶすという意味だそうです。
立春から新しい年の始まりと考えると、節分はその前日なので、大みそかのようなもの。
年越しそばのように「節分そば」を食べるところもあるそうです。
まとめ
- 節分は、立春を年の始めと考えた時代の特別な日。
- 鬼は季節の分かれ目に入り込んでくる厄災。
- 豆をまくのは、魔(ま)を滅(め)っするため。
- 豆以外にも、恵方巻、いわし、節分そばを食べる風習もあります。
- 高齢者には、豆は固いし危ないので、柔らかく炊いた豆を食べてもらおう!