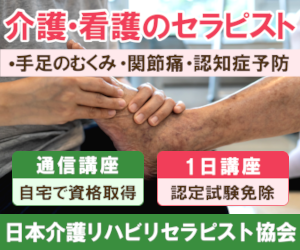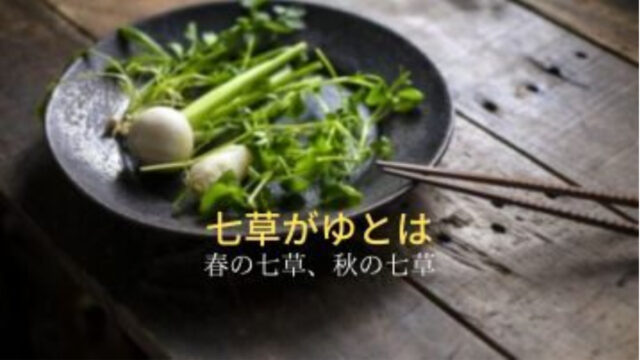スポンサーリンク

スポンサーリンク
寒露
10月8~23日頃。
「寒露」、寒い露ということなので、草木についた露が夜の大気の冷えによって冷たくなっているということを指しています。
人とご挨拶するときも「朝晩涼しくなりましたね」と言っていたのが、「朝晩冷えるようになりましたね」とか「朝晩肌寒くなりましたね」に変わってきますね。
七十二候
二十四節気寒露の候は以下の3つです。
初候: 鴻雁来る(がんきたる)

10月8~13日頃。
日本で冬を過ごすために、ガンやカモなどの冬鳥たちが飛来してきます。
飛来地として有名なのは
・北海道美唄市の宮島沼
・宮城県栗原市の伊豆沼など。
マガンやヒシクイがたくさん飛んできます。
【初雁(はつかり)】
その年初めてやって来たマガンのこと、秋の季語。
【雁渡し(かりわたし)】
冬鳥が飛んでくる頃に吹く北の風のこと、秋の季語。
次候: 菊花開く(きっかひらく)

10月14~18日頃。
菊が見ごろを迎えます。
菊の花は江戸時代にいろいろな種類が増え、菊を育てたり眺めたりするのは、身分を問わない娯楽として定着していきました。
今でも菊花展、菊祭り、菊の花で衣装を作った菊人形祭りなどが盛んに行われ、たくさんの人の目を楽しませています。
末候: 蟋蟀戸にあり(きりぎりすとにあり)

10月19~23日頃。
「蟋蟀」はキリギリスではなくコオロギという説もあります。
「戸にあり」とは、家の戸のすぐそばで鳴いているということ。
キリギリスを冬と見立てると、冬がもうすぐそこまで来てるよと言っています。
この頃になるとキリギリスやコオロギの鳴く声が、夕方ではなく真昼間も聞こえるようになります。
また見上げてみると、空にはモズが自分の縄張りを主張して高鳴きしています。