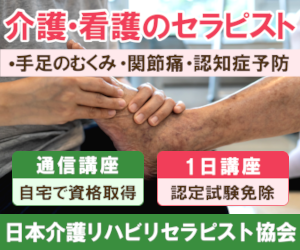スポンサーリンク
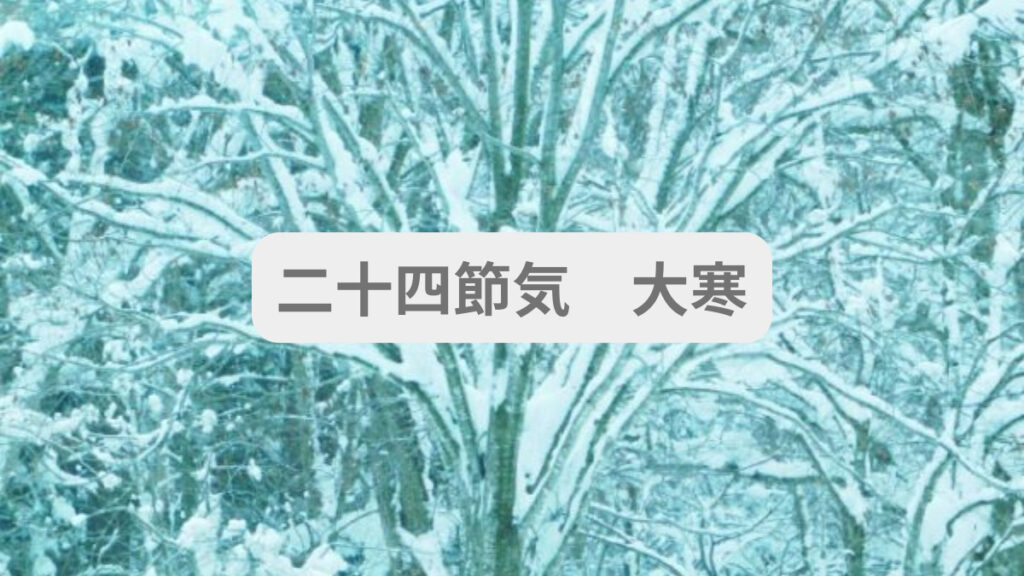
スポンサーリンク
大寒
1月20~2月3日頃。
二十四節気の最後です。
寒さも底を迎えるのがこの大寒です。
前の節気である「小寒」と合わせて「寒の内」といいます。
【寒の水】
この頃に汲まれる水で、一年の内でもっとも冷たくて澄んだ水です。
お酒や、味噌、醤油など清らかな水を必要とするところでは仕込み(「寒仕込み」)に忙しくなります。
【オリオン座】

冬を代表する星座。
南の空に現れる大きな星座です。
4つの星を結ぶと大きな四角ができ、その中に3つの星が並んでいます。
その姿が鼓に似ていることから和名は「鼓星」というそうです。
ちなみに日本一美しい星空が見れる場所として、環境省が「日本一星空観測に適した場所」と設定しているのは長野県下伊那郡阿智村です。
七十二候
二十四節気大寒の候は以下の3つです。
初候: 款冬華さく(ふきのとうはなさく)

1月20~24日頃。
フキノトウは全国の山野に自生している山菜のひとつで、フキの花になります。
この花のあとにフキが出てきます。
初春の食べ物として天ぷらや和え物として食べたりします。
独特の苦みが特徴です。
そのフキノトウは雪の下から顔を出す形で生えてきます。
次候: 水沢腹く堅し(みずさわあつくかたし)

1月25~29日頃。
大寒真っただ中で、沢の流れすらも厚い氷に変わってしまう頃という意味です。
北国の湖や滝なども日に日に氷が厚くなっていきます。
末候: 鶏初めて乳す(にわとりはじめてにゅうす)

1月30~2月3日頃。
にわとりが卵を産んで始め、子育てをする時期という意味です。
今では年中売ってある卵ですが、もともと旬は2~4月。
寒い時期は産卵量が減る分、雌の体内にいる時間が長くなるので栄養価がアップしているそうです。