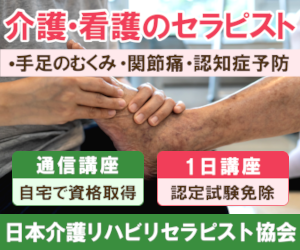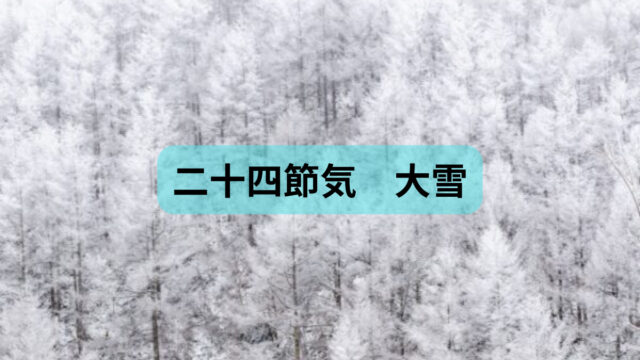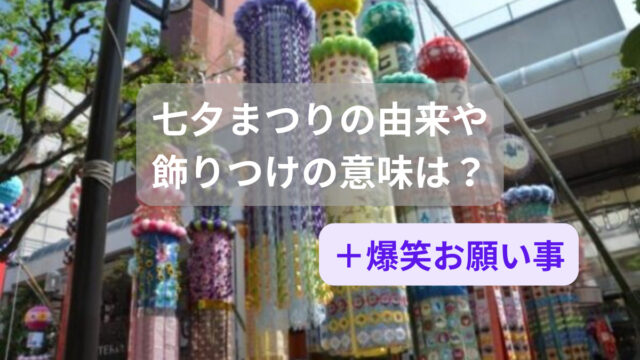立春
二十四節気のひとつ立春です。
2月4~18日頃です。
暦の上では立春から春が始まります。
雑節といわれる八十八夜や土用なども立春をもとにして数えます。
立春の日には「立春大吉」と書いた紙を柱に貼ると、一年を無事に過ごせるとされています。
それは「立春大吉」という字が左右対称になっているので、バランスがよく安定をイメージさせることから縁起がよいとされているようです。
「立春大吉」と貼った家に鬼が入り、振り返ると裏から見ても「立春大吉」となっていたので、まだ家に入ってなかったと勘違いした鬼が逆戻りして去っていったという逸話があります。
【旧正月】
旧暦では立春前後が元日となり、旧正月に入ります。
中国では「春節」といいますが、日本でも横浜や長崎の中華街ではお祭りが行われます。
【春一番】
立春から春分(3月21日頃)までの間に吹く、強い南風です。
春一番の吹いた日は気温が上がりますが、その後は寒くなります。
春の到来を知らせるうれしいお知らせのイメージですが、元々漁師さんの使っていた言葉で、長崎の壱岐では船が転覆し、大勢の人が亡くなったりしたこともあるという、ちょっと怖い風でもあります。
年によっては観測されない年もあります。
七十二候
二十四節気立春の候は以下の3つです。
初候: 東風凍りを解く(とうふうこおりをとく)

2月4~8日頃。
立春の初候です。
春風が氷を解かし始める頃という意味です。
陰陽五行の思想では、東は春をつかさどる方角にあたるので、東風は春風のことを指しています。
次候: 黄鶯睍睆く(うぐいすなく)

2月9~13日頃。
立春の次候です。
うぐいすは「春告鳥(はるつげどり)」といわれています。
実際咲くのはもう少し後、2月下旬あたりに九州から鳴き始め北上していきます。
「ホーホケキョ」はオスの求愛の鳴き声ですが、最初は「ぐずり鳴き」という下手くそな鳴き声です。
「ホケ、ホケ」という感じ。
末候: 魚氷に上る(うおこおりにのぼる)

2月14~18日頃。
立春の末候です。
湖や沢が少しぬかるみ、魚が顔を出す頃という意味です。
ちょうど渓流釣りが解禁になるころです。