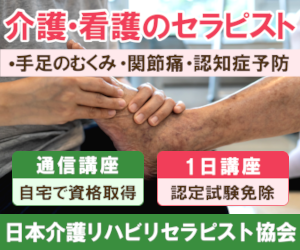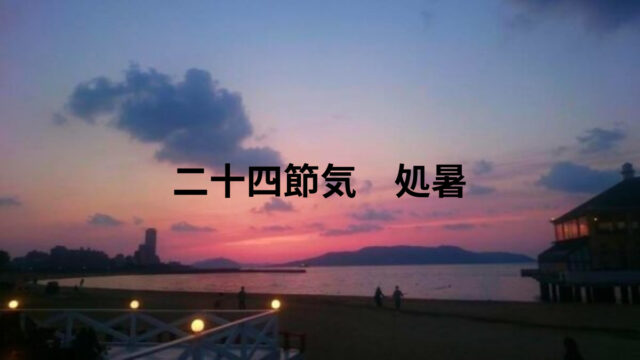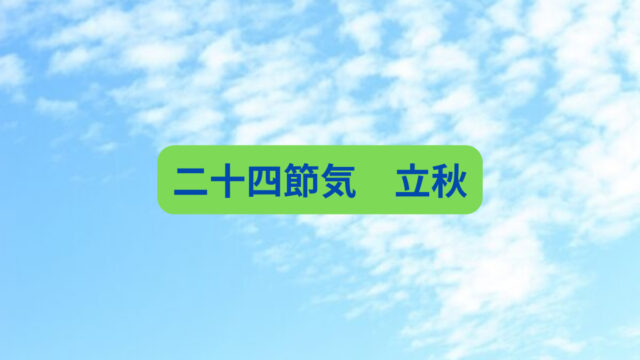スポンサーリンク

スポンサーリンク
立夏
5月6~20日頃。
暦の上では今日から夏です。
まだ7、8月のようなちりちりした本格的な夏と違って、さわやかな風が吹くからっとした気候です。
このさわやかな風を「薫風(くんぷう)」といいます。
「薫風」は、平安時代には花の香りを運ぶ春の風だったのが、江戸時代の俳諧の発展にともなって夏の季語になりました。
七十二候
二十四節気立夏の候は以下の3つです。
初候: 蛙始めて鳴く(かわずはじめてなく)

5月6~10日頃。
蛙が繁殖期を迎える時期です。
田んぼのそばでは夜中、オスの求愛の大合唱がきかれます。
蛙は自分の生まれたところに帰る習性があるそうで、縁起物として人気があります。
「お金がかえる」「運がかえる」ですね。
次候: 蚯蚓出ずる(みみずいずる)

5月11~15日頃。
ミミズが土から出てくる頃です。
ミミズは啓蟄のころではなく今頃出てきます。
昔からミミズのいる土地は豊かな土地と言われています。
ミミズの出す糞が土にとって栄養となり、またミミズが地中を動き回ることで、まるで鍬で耕したようなふかふかの土を作ることができるそうです。
末候: 竹笋生ず(たけのこしょうず)

5月16~20日頃。
たけのこが生えてくる時期です。
孟宗竹はすでに時期を過ぎている(3月頃)ので、この時期は「淡竹(はちく)」「真竹(まだけ)」「根曲がり竹」などです。
たけのこは採ってから早いうちに食べないとえぐみが出てきます。
栄養豊富で疲労回復や、塩分を排出するので高血圧にも効果があります。